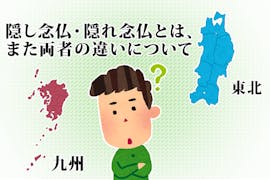 葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識 厳しい弾圧の中で人々がつないだ、隠し念仏・隠れ念仏とは?
隠し念仏とは、江戸時代の東北地方で、幕府に迎合した本願寺に不満を抱いた信徒が独自の信仰に走り、幕府と本願寺の両方から弾圧を受ける中、隠して守りぬいた信仰です。それに対し隠れ念仏とは、同じ江戸時代に九州で、浄土真宗の信徒が藩などの権力による弾...

2007年鎌倉新書入社。「月刊仏事」編集記者を経て、葬儀・お墓・仏壇など、終活・エンディング関連のお役立ち情報を発信する複数のWebメディアを立ち上げ。2018年には葬儀情報に特化した「はじめてのお葬式ガイド」をリリース。ライフエンディングコンサルタントとして「サンデーステーション」「Abema Prime」に出演するほか、「週刊女性」「介護ポストセブン」「マネーポストWEB」にコメント提供するなど、多方面で活躍中。
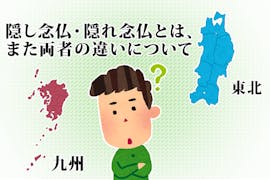 葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀後の手続き
葬儀後の手続き  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀の準備
葬儀の準備  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀の宗教・宗派
葬儀の宗教・宗派  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識 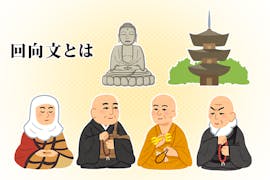 葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀の宗教・宗派
葬儀の宗教・宗派  葬儀の流れ
葬儀の流れ  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀の種類
葬儀の種類  服装と身だしなみ
服装と身だしなみ  葬儀のマナー
葬儀のマナー  お布施
お布施  法事・法要
法事・法要  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀の準備
葬儀の準備  葬儀後の手続き
葬儀後の手続き  葬儀の準備
葬儀の準備  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  仏壇・仏具
仏壇・仏具