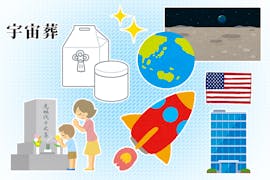 葬儀の種類
葬儀の種類 宇宙葬とは?やり方と費用の目安、メリット、注意点を解説
核家族化や高齢化が進んだ現代では、故人を送る方法も多様化してきています。最近では遺骨を宇宙で散骨する宇宙葬も話題を集めています。かつては一部の人に限られた宇宙葬でしたが、今では一般向けのサービスも提供され、その内容も、月面にカプセルを運んだ...

2007年鎌倉新書入社。「月刊仏事」編集記者を経て、葬儀・お墓・仏壇など、終活・エンディング関連のお役立ち情報を発信する複数のWebメディアを立ち上げ。2018年には葬儀情報に特化した「はじめてのお葬式ガイド」をリリース。ライフエンディングコンサルタントとして「サンデーステーション」「Abema Prime」に出演するほか、「週刊女性」「介護ポストセブン」「マネーポストWEB」にコメント提供するなど、多方面で活躍中。
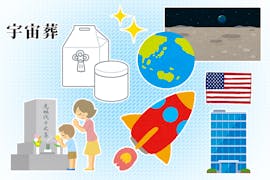 葬儀の種類
葬儀の種類  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  香典と香典返し
香典と香典返し  お墓・供養
お墓・供養  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀の準備
葬儀の準備  葬儀後の手続き
葬儀後の手続き  葬儀の種類
葬儀の種類  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  服装と身だしなみ
服装と身だしなみ  葬儀の準備
葬儀の準備  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀のマナー
葬儀のマナー お通夜や葬儀から帰宅する際、塩を振りかけるときは、胸・背中・肩・足元の順に塩をかけます。そして、床や地面に落ちた塩を踏んでから玄関に入ります。体を清めてから玄関をまたぐことで、穢れなどが家の中に入るのを防ぐという意味があります。このほかにも、塩を振るまえに水をかけて手を清めることがあります。
 終活映画
終活映画  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀の費用相場
葬儀の費用相場  葬儀の準備
葬儀の準備  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  法事・法要
法事・法要  葬儀の流れ
葬儀の流れ  葬儀のマナー
葬儀のマナー  有名人のお葬式・お別れ会
有名人のお葬式・お別れ会  葬儀の宗教・宗派
葬儀の宗教・宗派