親や家族が亡くなったあと、残された遺族はさまざまな手続きを行わなければなりません。
この記事では、死亡後から葬儀後の手続き、公的手続き、相続手続き、解約手続き、死亡後の供養と、5つに分けて詳しく解説していきます。
葬儀の準備・死亡後の手続きがわかる!
いい葬儀の手引きを無料ダウンロードする
目次
死亡後の手続き一覧チェックリスト(期限・窓口付)
親・家族の死亡後から葬儀後の手続き
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡診断書の受け取り | 死亡後すぐ | 病院 |
| 葬儀社手配とご遺体搬送・安置 | 死亡後すぐ | |
| 死亡届の提出と火葬許可証の取得 | 死亡日含め7日以内 | 市区町村役所 |
| 葬儀の準備・実施 | 死亡後数日以内 | |
| 葬儀後の対応 | 葬儀後すぐ |
親・家族の死亡後にする公的手続き
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 故人の公的年金受給停止 | 死亡後14日以内 | 年金事務所 |
| 故人の健康保険の資格喪失届 | 死亡後14日以内 | 市区町村役所など |
| 介護保険の解約 | 死亡後14日以内 | 市区町村役所 |
| 住民票の世帯主変更 | 死亡後14日以内 | 市区町村役所 |
| 雇用保険受給資格者証の返還 | 1か月以内 | ハローワーク |
| 高額療養費の還付 | 診察月の翌月1日を起算日として2年以内 | 市区町村役所など |
| 国民年金の死亡一時金の請求 | 死亡後2年以内 | 市区町村役所など |
| 国民健康保険の葬祭費の請求 | 死亡後2年以内 | 市区町村役所 |
| 健康保険の埋葬料の申請 | 死亡後2年以内 | 加入先の保険組合 |
| 生命保険の死亡保険金の請求 | 死亡後3年以内 | 加入先の生命保険 |
| 故人の未支給年金の請求 | 死亡後5年以内 | 年金事務所 |
| 遺族年金の請求 | 死亡後5年以内 | 年金事務所 |
親・家族の死亡後にする相続手続き
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 遺言書の確認・検認 | 3か月以内 | |
| 相続人・相続財産の調査 | 3か月以内 | |
| 遺産分割協議 | 3か月以内 | |
| 相続放棄 | 3か月以内 | |
| 所得税の準確定申告・納税 | 4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納税 | 10か月以内 | 税務署 |
親・家族の死亡後に必要な解約手続き
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 住居の賃貸契約 | できるだけ早く | 契約元 |
| 電気・ガス・水道 | できるだけ早く | 契約元 |
| 携帯電話・インターネット | できるだけ早く | 契約元 |
| NHK受信料 | できるだけ早く | 契約元 |
| クレジットカード | できるだけ早く | 契約元 |
親・家族の死亡後にする供養
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 香典返しの手配 | 四十九日まで | |
| 四十九日法要の手配 | 四十九日まで | |
| 納骨の手配 | 四十九日まで | |
| 本位牌・仏壇・お墓の手配 | 四十九日まで |
死亡後の手続きの優先順位・順番は?
- 親・家族の死亡後から葬儀後の手続き
- 親・家族の死亡後にする公的手続き
- 親・家族の死亡後にする相続手続き
- 親・家族の死亡後に必要な解約手続き
- 親・家族の死亡後にする供養
「死亡後から葬儀後の手続き」「死亡後の供養」は葬儀社に従って、スケジュール通り進めるべき。あとは期日の短い順番に「公的手続き」「相続手続き」を行うのが一般的です。ただし、料金のかかる「解約手続き」もできるだけ早い段階で対応しておいた方が安心。
内容や窓口、期日を把握して、スムーズに手続きを進めましょう。
親・家族の死亡後から葬儀後の手続き

死亡診断書の受け取り(死亡後すぐ)
親や家族が亡くなると、医師が死亡確認を行い、死亡診断書を作成します。死亡診断書は、亡くなった日時や場所、死亡の原因などが記載される書類。「人間の死亡を医学的・法律的に証明する書類」と「死因統計作成の資料」としての役割があります。また、事故や事件など、生前に診療していた傷病以外で亡くなった場合は死体検案書が交付されます。
死亡診断書と死体検案書は、どちらも同じ様式で表題は「死亡診断書(死体検案書)」です。亡くなった状況に応じて、どちらか一方を二重線で消して作成します。
死亡診断書は、役所や保険会社など、複数の場所へ提出する書類です。市役所・役場に提出すると戻ってこないので、コピーをとっておくか複数枚発行してもらいましょう。
病院で亡くなった場合
病院で亡くなると、遺体は死後しばらく霊安室に保管されます。保管されている間に、遺族は葬儀社を探して、遺体の搬送を依頼しなければなりません。
遺体搬送の手配ができたら、入院費の清算や退院手続きを行い、死亡診断書を書いてもらいます。遺体搬送には「死亡診断書の携行が義務付けられている」という言説があるため、死亡診断書を持っている人が同乗してください。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に連絡して死亡診断書を作成してもらいます。かかりつけ医がいないなら、救急車を呼んで病院まで搬送してもらいましょう。
ただ、療養していないのに突然亡くなった場合は、遺体を動かさず警察に連絡してください。事故・自死などで亡くなった方は、監察医・検視官が検死を行い、死体検案書を作成します。かかりつけの医師がいる場合は、あわせて連絡しておきましょう。
葬儀社手配とご遺体搬送・安置(死亡後すぐ)
故人のご遺体を搬送・安置する必要があるため、まずは葬儀社を手配します。ご遺体は、自宅または葬儀社・斎場に安置するのが一般的です。
自宅安置では、白いシーツをかけた布団にご遺体を寝かせます。掛け布団や枕も白色に揃え、宗派や地域の習わしにのっとり、枕飾りを整えます。必要なものや枕飾りを用意してくれる葬儀社もあるので、確認しておくとよいでしょう。自宅安置できない場合は、葬儀社や斎場、安置施設でのお預かり安置になります。
死亡届の提出と火葬許可証の取得(死亡日含め7日以内)
死亡届の提出
提出場所
- 故人の本籍地・死亡した場所・届出人の現住所のいずれかの市区町村役所
提出期限
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外で死亡した場合は事実を知った日から3か月以内
提出書類
- 死亡診断書(死体検案書)
- 死亡届
- 届出人の印鑑 など
死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、死亡届を提出します。死亡届は死亡診断書と一体になっていて、A3用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届です。
死亡届の提出先は、故人の本籍地・死亡した場所・届出人の現住所のうち、いずれかの市区町村役所。死亡の事実を知った日から7日以内の提出が義務づけられています。休日・夜間も受け付けているので、なるべく早めに提出してください。
火葬許可証の交付
提出場所
- 死亡届を提出した市区町村役所
提出期限
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外で死亡した場合は事実を知った日から3か月以内
提出書類
- 死亡届
- 火葬許可申請書
死亡届が受理されると、その場で火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は、ご遺体を火葬するための許可証で、火葬場の受付に提出しなければなりません。火葬が終わると、火葬許可証から埋葬許可証となり、納骨に必要になるので必ず受け取りましょう。
なお、死亡届の提出や火葬許可証の取得は、葬儀社が代行してくれます。
葬儀の準備・実施(死亡後数日以内)
打ち合わせ・日程決定
一般的には、ご遺体搬送・安置を依頼した葬儀社に、そのまま葬儀の施行までおまかせします。
葬儀の担当者と打ち合わせを行い、葬儀の日時、場所、内容などを決定していきます。日程は、菩提寺のお坊さん、火葬場・斎場の空き、参列者の予定をふまえて決めるため、死亡後1〜3日以内になる葬儀が多いです。また、葬儀会場を選ぶときは、参列者の人数や交通の便なども考慮してください。
関係者への連絡・訃報連絡
葬儀の日程・場所・内容が決定したら、親せきや故人の関係者、勤務先などに連絡します。また町内会・自治会に入っている場合は、責任者にも連絡しておきましょう。
葬儀後の対応(葬儀後すぐ)
精算・台帳整理
精進落としの終了後は、芳名帳、香典帳、香典、供花・供物帳、弔辞・弔電、支出金の領収書などを世話役から受け取り、事務の引き継ぎをします。
とくに現金は、トラブルを避けるためにしっかり確認し合う事が大切です。 引き継いだ書類は厳重に保管し、葬儀社の見積もりや明細書、請求書なども受け取っておきます。
支払い
引継ぎのあと、お手伝いしてくれた世話役に謝礼を、近所の奥さん達に心づけを渡します。金額は時代や地域によって変動するため、葬儀社の人に確認しておくと安心です。
葬儀社への支払いは、後日請求書が来るので対応しましょう。その他、斎場や仕出し店の精算も、忘れないよう早めに済ませてください。
挨拶回り
喪主または遺族は、葬儀終了後か翌日に挨拶回りをします。
まず寺院や自治会長(葬儀委員長)のお宅に伺い、それから故人と関係が深い順にまわるのがよいでしょう。手伝っていただいたり、供花、お供物、弔電を受け取ったりした近隣の方へのご挨拶も忘れずにしてください。とくにお世話になった方には、お礼の品を持参する場合もあります。
挨拶回りの服装は、地味であれば平服でも構いませんが、男性はネクタイを着用しましょう。
親・家族の死亡後にする公的手続き

故人の公的年金受給停止(死亡後14日以内)
提出場所
- 年金事務所、年金相談センター
提出期限
- 国民年金は亡くなった日から14日以内
- 厚生年金は亡くなった日から10日以内
提出書類
- 年金受給権者死亡届
- 年金証書
- 死亡を証明できる書類(死亡診断書の写しや戸籍など) など
故人が年金を受け取っていた場合、受給停止の手続きが必要です。国民年金は亡くなった日から14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所か年金相談センターへ年金受給権者死亡届を提出します。
提出時には死亡した人の年金証書と、死亡診断書や戸籍抄本など死亡の事実を証明できる書類が必要です。なお、日本年金機構にマイナンバーを登録している方は省略できます。
故人の健康保険の資格喪失届(死亡後14日以内)
提出場所
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者は居住地の市区町村役所
- その他の健康保険組合加入者は加入先の保険組合
提出期限
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者は死亡後14日以内
- その他の健康保険組合加入者は死亡後5日以内
提出書類
- 資格喪失届
- 保険証
- 死亡を証明できる書類(死亡診断書の写しや戸籍など) など
日本では、自営業者は国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療保険、会社員は協会けんぽや健康保険組合に加入しています。親や家族が亡くなった場合、資格喪失届を提出しなければなりません。
国民健康保険・後期高齢者医療保険は死亡後14日以内に市区町村役所へ、協会けんぽや健康保険組合は死亡後5日以内に年金事務所へ資格喪失届を提出します。会社員の方の場合、退職手続きとまとめて対応してくれる会社がほとんどです。また資格喪失届を提出するタイミングで、故人の扶養に入っていた被扶養者は、新たに国民健康保険に加入します。
介護保険の解約(死後14日以内)
提出場所
- 市区町村役所の介護保険担当窓口、介護保険課
提出期限
- 死亡後14日以内
提出書類
- 介護保険資格取得・異動・喪失届
- 介護被保険者証
- 本人確認書類
- (あれば)介護保険負担限度額認定証 など
故人が65歳以上(第1号被保険者)、または40歳から64歳未満で介護保険の被保険者(第2号被保険者)の場合、死亡後に介護保険の資格喪失手続きをしなければいけません。
手続きは、故人の死亡後14日以内に、相続人が各市区町村の介護保険担当窓口や介護保険課で行います。介護保険の解約には、介護保険資格取得・異動・喪失届が必要です。各市区町村の役所で入手をするか、ホームページからダウンロードをします。
介護保険資格取得・異動・喪失届を記入したら、介護被保険者証と合わせて提出してください。マイナンバーと本人確認書類、発行されていた場合は介護保険負担限度額認定証もあわせて提出します。
なお、40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていない人は、介護被保険者証を持っていないので手続きは扶養。死亡届を提出した時点で、介護保険は解除されます。
介護保険の未納保険料と還付金
介護保険の未納分は、相続人に請求されます。介護保険の納付義務は、死亡した翌日の前月分まで。たとえば被保険者が「3月30日」に亡くなった場合、翌日である「3月31日」の前月まで、つまり2月分までに納付義務が課せられます。もし「3月31日」といった月の最終日に亡くなった場合は、翌日が「4月1日」などの月初めになるため、3月分までが納付義務です。
反対に、保険料を納めすぎている場合は、相続人に還付金が還付されます。還付金があった場合、申請した役所から「過誤状況届出書」が届くので、記入して返送しましょう。記載した相続人の口座に還付金が振り込まれます。
要介護・要支援認定の申請中に亡くなった場合
要介護・要支援の申請中に亡くなった場合も、届け出が必要です。各市区町村の役所で「要介護・要支援認定等申請取下げ申出書」を取得、またはホームページでダウンロードして、用紙に記載し、介護保険課の窓口に提出します。介護支援の申請時には訪問調査などもありますので、死亡後はなるべく早く手続きしましょう。
住民票の世帯主変更(14日以内)
提出場所
- 市区町村役所
提出期限
- 死亡後14日以内
提出書類
- 世帯主変更届
- 届出人の本人確認書類
- 届出人の印鑑 など
故人が世帯主で、家族が新たに世帯主になる場合は、世帯主を変更しなければなりません。世帯主変更届は、故人の死後14日以内に住んでいる市区町村役所へ提出します。届出人の本人確認書類や印鑑が必要なので、用意しておいてください。
雇用保険受給資格者証の返還(1か月以内)
提出場所
- 故人が雇用保険を受給していたハローワーク
提出期限
- 死亡後1か月以内
提出書類
- 雇用保険受給資格者証
- 死亡を証明できる書類(死亡診断書の写しや戸籍など) など
故人が雇用保険を受給していた場合、雇用保険受給資格者証を返還します。死亡後1か月以内に、故人が雇用保険を受給していたハローワークへ雇用保険受給資格者証を提出しましょう。
高額療養費の還付(診察月の翌月の1日を起算日として2年以内)
提出場所
- 市区町村役所、健康保険組合など
提出期限
- 診察月の翌月1日を起算日として2年以内
提出書類
- 高額療養費支給申請書
- 医療費の明細書 など
高額療養費制度とは、1か月の医療費が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって違いますが、生前の治療で医療費が超過しているなら、加入先の市区町村役所や健康保険組合に申請すれば還付金を受け取れます。
国民年金の死亡一時金の請求(死亡後2年以内)
提出場所
- 市区町村役所、年金事務所、年金相談センター
提出期限
- 死亡後2年以内
提出書類
- 国民年金死亡一時金請求書
- 故人の年金手帳(基礎年金番号がわかる書類)
- 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
- 世帯全員の住民票の写しまたはマイナンバー
- 死亡者の住民票の除票
- 受取先口座がわかるもの
国民年金の第1号被保険者として36月以上保険料を納めている方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、遺族は死亡一時金を受け取れます。
国民年金の死亡一時金は、死後2年以内に、故人が居住していた市区町村役所か年金事務所、年金相談センターへ申請します。なお、遺族基礎年金を受け取る場合は、死亡一時金は支給されません。
国民健康保険の葬祭費の請求(死亡後2年以内)
提出場所
- 市区町村役所
提出期限
- 死亡後2年以内
提出書類
- 葬祭費支給申請書
- 故人の国民健康保険証
- 葬祭費用の領収書(喪主の氏名と葬儀の実施を確認できる書類)
- 受取先口座がわかるもの
故人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合、市区町村役所に申請すれば葬祭費を請求できます。自治体によって金額は違いますが、死亡後2年以内に書類を揃えて申請しましょう。
健康保険の埋葬料の申請(死亡後2年以内)
提出場所
- 故人が加入していた健康保険組合や協会けんぽ
提出期限
- 死亡後2年以内
提出書類
- 埋葬料(費)支給申請書
- 故人の健康保険証
- 葬祭費用の領収書(喪主の氏名と葬儀の実施を確認できる書類)
- 死亡を証明できる書類(死亡診断書の写しや戸籍など) など
故人が健康保険組合や協会けんぽなどの社会保険に加入していた場合、埋葬料が支給されます。埋葬料は一律5万円で、死亡後2年以内に保険の加入先へ必要書類を提出すれば受け取れます。
生命保険の死亡保険金の請求(死亡後3年以内)
提出場所
- 故人が加入していた生命保険
提出期限
- 死亡後3年以内
提出書類
- 保険証書(証券)
- 故人の住民票
- 死亡診断書(死体検案書)
- 届出人の戸籍抄本 など
故人が生命保険に加入していた場合、指定されている保険金受取人は保険金を受け取れます。加入している生命保険によって必要な書類が違うので、まずは連絡を入れてみましょう。
故人の未支給年金の請求(死亡後5年以内)
提出場所
- 年金事務所、年金相談センター
提出期限
- 死亡後5年以内
提出書類
- 年金受給権者死亡届
- 未支給【年金・保険給付】請求書 など
年金受給者が亡くなったとき、受け取っていない年金は未支給年金として遺族が受け取れます。ただ、受け取れる権利があるのは、受給者が死亡した当時、生計を同じくしていた遺族だけ。未支給年金を受け取るには、死亡後5年以内に、年金受給権者死亡届と未支給【年金・保険給付】請求書の届け出が必要です。
遺族年金の請求(死亡後5年以内)
提出場所
- 年金事務所、年金相談センター
提出期限
- 死亡後5年以内
提出書類
- 年金請求書 など
年金の受給前に亡くなった場合、故人によって生計を維持されていた遺族は遺族年金を受け取れます。遺族年金の種類には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金などがあり、支給対象や年金額が変わるので事前に確認しておきましょう。
親・家族の死亡後にする相続手続き

遺言書の確認・検認(3か月以内)
相続手続きを行うにあたり、まずは最優先で遺言書の有無を確認します。
故人が自分で書いた自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。遺言書を検認せずに開封すると、5万円以下の過料が発生する可能性があるので注意しましょう。また、法律の専門家が代筆した公正証書遺言であれば、公証役場に保管されています。
相続人・相続財産の調査(3か月以内)
遺言書があれば、遺言通りの相続人へ財産が分割されるのが一般的。遺言書がない場合、相続人と相続財産の調査を行わなければなりません。
相続人を調べるには、故人が生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本を取得する必要があります。故人の本籍地がある市区町村役所の窓口に申請するか、郵送で取り寄せて相続人調査を行いましょう。
相続人がわかったら、故人の相続財産を調査します。故人が生前取引していた口座や証券、不動産などを確認し、各機関へ問い合わせして、所有財産を明確にしてください。
遺産分割協議(3か月以内)
遺言書がない場合は、相続人と相続財産が確定したあと、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合い、合意すること。
当事者間で解決できない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停をしなければなりません。遺産相続はトラブルに発展しやすいため、心配なら早めに弁護士への依頼を検討しましょう。
ちなみに、遺産分割協議には明確な期限が決まっていません。ただ相続放棄の判断をするなら3か月、相続税の申告をするなら10か月以内に行うのが望ましいです。
相続放棄(3か月以内)
相続放棄とは、相続人が故人の資産・負債の継承を拒否すること。相続人は、預金や土地などのプラスの遺産だけでなく、借金や負債などのマイナスの遺産も引き受けます。故人に多額の負債があった場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。
また、プラスの遺産を限度にマイナスの遺産を相続する限定承認を活用するのもひとつの方法です。
所得税の準確定申告・納税(4か月以内)
故人が個人事業主、または年収2000万円以上の給与所得者だった場合、相続人が確定申告をしなければなりません。相続人が故人の代理で確定申告を行うことを「準確定申告」と呼びます。
準確定申告は、相続開始を知った翌日から4か月以内に、故人の死亡当時の税務署で行います。相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添えて、確定申告書を提出しましょう。
相続税の申告・納税(10か月以内)
遺産の分割方法が決まったら、相続税を計算し、故人の住所地の税務署に申告・納税します。
相続税の申告期限は、故人の死亡を知った日の翌日から10か月以内。期限を過ぎたり、計算を間違えたりすると、追徴課税を受けるかもしれません。相続財産が多かったり、不動産が含まれていたりする方は、税理士などの専門家に依頼した方が確実です。
相続に強い士業を無料で紹介!
相続手続きにお悩みなら「いい相続」へ
親・家族の死亡後に必要な解約手続き
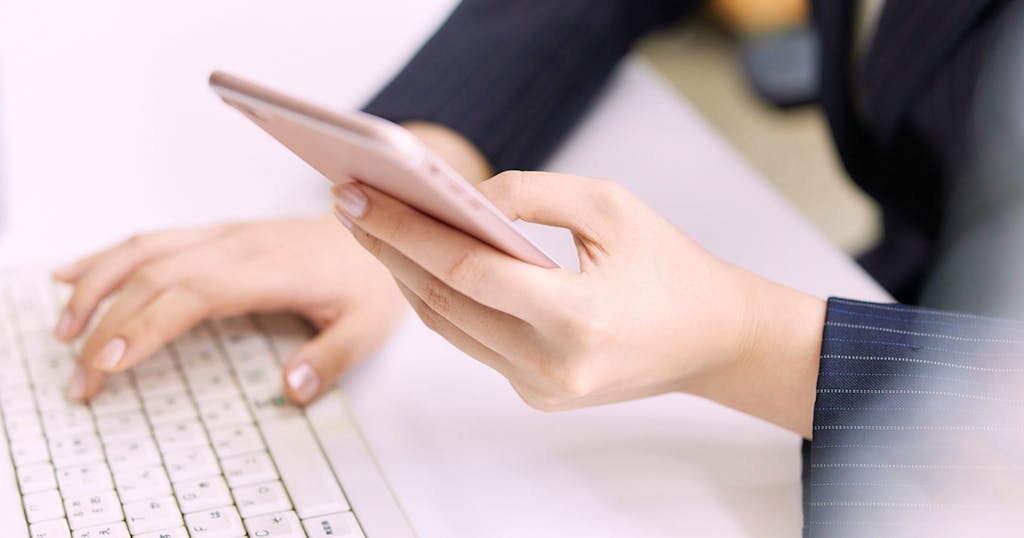
住居の賃貸契約
賃貸に住んでいた場合、賃貸借契約を結んでいます。賃貸借契約は死亡しても消滅せず、家賃の支払い義務や未払いの債務などが相続人に承継されます。
居住の必要がない場合、故人の住居はすみやかに解約すること。解約することで、連帯保証人の連帯保証契約も自動的に消滅します。保証人への通知は必要ありませんが、故人や遺族との関係性によっては知らせてあげましょう。また、解約で戻ってきた敷金は相続人の代表が受け取ります。
電気・ガス・水道
賃貸契約と同様、居住の必要がない家の電気・ガス・水道は解約手続きをします。引っ越しや清掃をする場合は、必要な作業がすべて終わってから解約した方がベター。ただ、解約の締め日を越えないように解約すると、費用をおさえられるので意識するとよいでしょう。
同居の家族がいて、電気・ガス・水道を継続使用する場合は、名義変更の手続きをします。
携帯電話・インターネット
故人の携帯電話を解約するには、死亡が確認できる書類と届出人の身分証明書、本人の契約書類、SIMカードなどを持参して手続きします。キャリア各社により手続き方法が異なる可能性があるので、お店へ行く前に電話やホームページなどで確認しておきましょう。
また、故人の携帯電話を遺族が使い続ける場合は、契約期間やポイントが承継されるか改めて確認が必要です。インターネットの固定回線やポケットWi-Fiなどの通信機器を契約していた場合は、契約元に連絡して停止の手続きをします。
NHK受信料
故人が一人暮らしでNHKの受信契約をしたまま亡くなり、解約手続きを取らずにいたために死後の分まで遺族が請求を受けたケースがあります。遺族が故人の家に住んでテレビを使用するわけではなければ、すみやかにNHKのフリーダイヤルに連絡して解約しましょう。
状況を説明することで、解約月を亡くなった月に変更したり、死後の自動引き落としを過払い金として返還してもらえたりするかもしれないので、相談してみるのがおすすめです。
クレジットカード
クレジットカードは、使用がなくても年会費などが発生するかもしれません。カード会社に連絡すれば、すぐに会員資格の取り消し処理が行われるので、できるだけ早く連絡してください。
親・家族の死亡後にする供養

香典返しの手配
香典返しは、香典をいただいたお礼として、遺族が参列者にお返しする品物。四十九日法要が終わった翌日から1か月以内にお返しするのが一般的なので、手配を進めておきましょう。
香典返しの金額相場は、いただいた香典金額の半分程度を返す「半返し(半分返し)」。飲み物や食べ物、消耗品などの「消えもの」を贈るのが定番です。
四十九日法要の手配
四十九日法要は、故人が亡くなった49日目を目安に行う法要です。四十九日は、喪に服していた遺族が日常生活にもどる「忌明け(きあけ)」にあたり、盛大に故人の供養を行います。
四十九日法要では、日程・会場の決定はもちろん、本位牌・仏壇・お墓の準備やお坊さんの手配などが必要です。準備すべきことが多いため、余裕をもって1か月前にははじめましょう。
お付きあいのあるお寺がない方は「いいお坊さん」
四十九日法要4.5万円から僧侶をご紹介します
納骨の手配
納骨とは、遺骨をお墓や納骨堂に納めること。納骨のときに行われる式が「納骨式」です。
納骨する時期に決まりはありませんが、四十九日法要をあわせて行うのが一般的。四十九日法要と納骨式を一緒に行うなら、同時に準備を進めておきます。
本位牌・仏壇・お墓の手配
四十九日までに、故人の魂を白木位牌から本位牌へ入れ替えます。 彫刻には2週間ほどかかるので、早めに準備しましょう。
また、仏壇やお墓がない家庭では、あわせて用意するケースが多いようです。四十九日法要や納骨式と一緒に、本位牌・仏壇・お墓の手配も行います。


専門家の代行で死亡後の手続きをスムーズに
親や家族が亡くなると、葬儀・法要と並行しながら、変更届の提出や解約、お金の請求、相続など、さまざまな手続きを行わなければなりません。とくに公的手続き・相続手続きは、期日やルールが決まっていて、煩雑になりやすいです。ご遺族だけで進めると、手続きが漏れたり家族間でトラブルに発展したりする危険性があるので注意してください。
相続税の申告・納税や遺産の名義変更といった相続手続きは、司法書士や税理士などの専門家に代行してもらうのもひとつの方法。
いい葬儀の姉妹サイト「いい相続」では、相続・遺言の専門家探しを無料でサポートしています。死亡後の手続きをスムーズにし、負担を軽くするお手伝いをしますので、ぜひお気軽にご相談ください。








