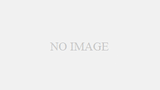一般的な葬儀の流れは「ご逝去→葬儀前→通夜・葬儀→火葬・散会→葬儀後」の5段階にわけられます。葬儀を開催する喪主と親族は、細かな手続きや打ち合わせ、儀式など、やるべきことがたくさん。家族が亡くなったとき慌てず対応できるよう、事前に葬儀・葬式の流れを確認しておくと安心です。
この記事では、一般的なお葬式の流れをご紹介。亡くなってからお葬式をするまでの正しい手順やかかる日数、儀式の内容などについて詳しく解説します。
葬式・葬儀の基本的な流れ

こちらは、亡くなってから葬儀後までの流れを一覧にまとめた表です。葬儀の流れは、「ご逝去」「葬儀前」「通夜・葬儀」「火葬・散会」「葬儀後」と大きく5段階にわけられます。
ご家族が危篤になり、ご逝去されたら、まずは死後の儀式や手続きを行います。それから葬儀社を手配し、遺体の搬送・安置や葬儀の打ち合わせなど、葬儀前の準備をスタート。そして通夜・葬儀のあと、火葬を行い、故人と最期のお別れをして散会します。葬儀後は、関係者へのお礼や手続きが必要です。
一般的には、故人が亡くなった翌日に通夜を行い、翌々日に葬儀・告別式を行います。ただ火葬場の空きや僧侶のスケジュールによって前後するため、実際にかかる平均日数は3日~5日ほど。(※参考記事)臨終後、早めに遺体の搬送を求める病院もあり、逝去後は速やかに葬儀社を選び、安置先を決めなければなりません。
ここからは、項目ごとに葬儀の流れについて解説していきます。
ご逝去

| ご逝去 | 危篤 |
| 逝去(臨終) | |
| 末期の水 | |
| 死亡届の提出 |
危篤
危篤とは、病気やケガによって生命に危機が迫っている状態。回復の見込みがなく、いつ臨終してもおかしくありません。医師から危篤を告げられたら、家族や親族などの近親者に連絡を入れましょう。
3親等以内が一般的ですが、故人が最期に会いたい可能性のある人には、心残りがないよう連絡をしておいた方がベター。危篤連絡は電話で行い、つながらなかった場合だけメールを入れるのが基本的なマナーです。また、もし危篤状態が長引くようなら、職場への連絡も忘れずしてください。
逝去(臨終)
故人様のご逝去(臨終)後は、医師による死亡確認が行われます。
死亡宣告を受けたら、亡くなった事実を伝えるために、親しい方へ訃報連絡を入れてください。葬儀の日取りや場所が決まったら改めて訃報連絡するので、ここでは家族や親族のみに連絡しましょう。手段や内容は問われないため、連絡しやすい方法を選んで問題ありません。
末期の水
末期の水とは、臨終に立ち会った近親者が故人の口に水を含ませる儀式。宗旨宗派によって違いますが、医師から臨終を告げられたタイミングで末期の水を執り行うことが多いです。
末期の水では、茶碗に入れた水を用意し、新品の割り箸の先に脱脂綿を巻きつけます。血縁関係の近い故人の配偶者や子ども、親の順番に、水に浸した脱脂綿で故人の唇を湿らせていきます。
病院で亡くなった場合、医療スタッフの方が誘導してくださるので指示に従いましょう。
死亡届の提出
死亡届とは、故人が亡くなったことを役所に知らせる書類です。
家族が逝去すると、医師による死亡確認と死亡診断書の作成が行われます。自宅で逝去を迎えた場合はかかりつけ医に連絡をし、指示を仰ぎましょう。もしかかりつけの医師に連絡がつかないのであれば、病院の救急外来に連絡します。
死亡届は、医師から渡される死亡診断書とセットになっていることが多いです。医師の死亡診断書をもとに、死亡届を作成して提出してください。死亡届は逝去から7日以内に提出しなければなりませんが、葬儀社にお願いすると代行してくれます。
葬儀前

| 葬儀前 | 葬儀社手配 |
| 遺体搬送 | |
| 遺体安置 | |
| 葬儀の打ち合わせ | |
| 訃報連絡 |
葬儀社手配
故人が亡くなったら、速やかに葬儀社を手配します。病院の霊安室は数時間しか利用できないため、葬儀社に依頼して遺体を安置場所へ移動しなければなりません。
葬儀社を紹介してくれる病院もありますが、オススメなのは複数の葬儀社を比較・検討すること。なぜなら、予算や参列人数、宗旨宗派などの条件によって最適な葬儀社が変わるからです。ご逝去前から条件に合う葬儀社を探しておけば、スムーズにお葬式の準備を進められます。
ちなみに病院から紹介された葬儀社に遺体の搬送だけお願いして、葬儀は別の葬儀社に依頼しても問題ありません。時間的・精神的余裕がないかもしれませんが、できるだけ慎重に葬儀社を選ぶことで、後悔のないお葬式にできるでしょう。
遺体搬送
故人の遺体は、葬儀社の車で安置場所に搬送されます。安置場所は自宅や斎場、火葬場、葬儀社などが一般的です。家族や葬儀社と相談しながら、遺体の搬送先を決定しましょう。
ちなみに遺体を搬送できるのは、国土交通省から許可を受けた事業者のみ。身内の自家用車で運ぶのは法律違反になりませんが、安全性の観点から専門の葬儀社や搬送業者に依頼するのが一番です。
遺体安置
故人の遺体は死後24時間火葬できないため、通夜・葬儀までの間、指定の場所に安置されます。以前は自宅が一般的でしたが、最近は火葬場や斎場など、通夜・葬儀を行う施設に安置するご遺族が多いです。
火葬場・斎場には、霊安室や保冷庫、遺体安置室があり、遺族が付き添ったり仮眠したりできる施設が用意されています。ただし、面会時間に制限があったり料金がかかったりするケースもあるため、利用前に確認しておきましょう。
葬儀の打ち合わせ
家族の打ち合わせ
遺体の安置が終わったら、葬儀の打ち合わせに入ります。可能であれば、葬儀社より先に家族だけでどんなお葬式にしたいか話し合っておくとスムーズです。
宗派の確認や喪主の決定、遺影写真の選別、予算のすり合わせなど、故人の遺言をふまえて方向性を決めておきましょう。
葬儀社の打ち合わせ
ご遺体を安置したら、家族や葬儀社と葬儀の打ち合わせをします。まず仮で葬儀の日程を決め、お葬式をする斎場や火葬場など、詳細を検討するのが一般的です。
- 喪主
- 葬儀の宗教・宗派
- 葬儀の規模・形態
- 葬儀のプラン・費用
- 葬儀の日時・場所
- 棺や祭壇、供花などの葬祭用品
- 通夜ぶるまいや精進落としなどの接待料理
- 当日返しや香典返しなどの返礼品
などを、参列人数や予算、お坊さんの空き状況にあわせて決めていきます。
宗教者(お坊さん)の手配
仏式の葬儀では、読経や戒名付与をしてもらうために、お坊さんの手配が必要です。普段からお世話になっている菩提寺がある場合は、連絡して僧侶を手配しましょう。菩提寺のお坊さんの予定が空いていれば、葬儀の日程を確定できます。
もし菩提寺がない場合は、僧侶手配サービスを利用するのがオススメ。葬儀の日程に合わせて、全国各地のお坊さんを紹介してくれます。
葬儀の風習は地域によって違う?
葬儀には、地域特有の風習や一族のしきたりが残っていることが多いので注意してください。
たとえば都市部では、家族が葬儀の方針を決め、セレモニーホールで通夜・葬儀を行うのが一般的。ですが地方では、家族だけでなく、親戚やご近所さんと話し合いをして方向性を固め、自宅かお寺でお葬式をするご遺族が多いです。
お住まいの地域の風習を確認して、土地のしきたりに則った葬儀をあげるように心がけましょう。
葬儀のやり方が遺言で残されていたら?
遺言の内容には、法的な強制力のある「遺言事項」と法的な強制力のない「付記事項」があります。
葬儀のやり方は付記事項にあたり、決定権は相続人にあるため、実行する必要はありません。故人の遺志を汲みつつ、無理のない範囲で実現すればよいでしょう。
訃報連絡
通夜・葬儀の日時や場所が決まったら、あらためて訃報連絡を行います。
- 家族
- 親族
- 友人・知人
- 職場・学校の関係者
- 町内会・自治会
連絡の優先順位は、親族、友人、知人、職場・学校の順番。親族は3親等(故人から見て甥・姪、ひ孫など)までを目安にしてください。
訃報連絡の手段は電話が多いようですが、状況によってはメールでもかまいません。故人の訃報を伝えるとともに、葬儀の案内を行いましょう。故人と親しかった友人、知人には生前家族がお世話になった感謝の気持ちも伝えます。
また家族だけで葬儀を行う場合は、お葬式に参列者を招かず、家族だけで見送る旨を丁重に案内しましょう。葬儀が終わったあとにハガキや手紙で訃報連絡を送るのも、方法のひとつです。
新聞の訃報広告は出すべき?
新聞の訃報広告は、連絡の手間を省いて、スピーディーに訃報を届けられるのがメリット。故人が世間的に有名だったり、社会的地位が高かったりする場合はもちろん、地域によっては一般の方も新聞の訃報広告を利用しています。
新聞の訃報広告は、直接新聞社に申し込むか、葬儀社や広告代理店に手続きを代行してもらって掲載するのが基本です。掲載するエリアや広告のサイズによって料金が変わるため、事前に確認しておきましょう。
通夜・葬儀

| 通夜・葬儀 | 湯灌(ゆかん) |
| 死化粧 | |
| 納棺 | |
| 通夜 | |
| 通夜振る舞い | |
| 葬儀・告別式 |
湯灌(ゆかん)
湯灌(ゆかん)とは、故人の遺体をお風呂に入れて洗い清める儀式。葬儀社や湯灌師が納棺前に行うのが一般的で、故人の体をキレイにして身なりを整えるのが目的です。
湯灌は必須ではないので、ご遺族の意向にあわせて行うかどうか判断して問題ありません。葬儀社に依頼すると5〜10万円ほどオプション料金が必要になるため、予算や希望に応じて決めましょう。
死化粧
死化粧とは、遺体を清め、髪や身なりを整えて化粧を施すこと。湯灌と似ていますが、お湯を作る儀式や入浴がなく、遺体を美しく整えることを目的に行います。
死化粧の料金は、依頼先によって違うため、事前に確認しておくと安心です。
納棺
納棺とは、亡くなった人を棺に納める儀式。湯灌やエンゼルケア、死化粧などで身なりを整えたあと、副葬品と一緒に故人を棺に納めます。また地域によっては、納棺前に「末期の水」を行います。
棺に納める副葬品は、故人の愛用品や好きだったものが一般的ですが、燃えずに残る物品はNGです。金属やガラス、プラスチック製品はもちろん、水分の多いフルーツや分厚い本、メガネなども入れられないので注意してください。
通夜
一般的な葬儀は2日間あり、1日目にお通夜を行います。
通夜は、葬儀の前日に故人と最期の夜を過ごす儀式。本来通夜は、夜通し故人の遺体を見守る儀式でしたが、現代では18時前後から1〜3時間ほど行う「半通夜」が一般的です。仏式であれば僧侶の入場、読経、焼香と続き、最後に喪主が挨拶をして閉式します。
通夜振る舞い
通夜の閉式後、参列した弔問客や手伝ってくださった方々に食事や酒をふるまいます。これは通夜振る舞いと呼ばれ、弔問客へ感謝を伝えること、思い出を語り合って故人を偲ぶことが目的です。また、「故人と最後の食事を共にしてもらう」といった意味合いもあります。
通夜ぶるまいに誰を呼ぶかは、遺族の意向や地域によってさまざまです。わからない場合は年配の親族か葬儀社の担当者に尋ねるとよいでしょう。
葬儀・告別式
葬儀・告別式は、故人と最期のお別れをする儀式。火葬の時間にあわせて開式し、葬儀〜散会までは5時間前後かかるのが目安です。
参列者が着席すると、僧侶が入場して読経します。宗派によって異なりますが、読経時間は30分〜60分ほど。読経とともに故人に戒名が授けられ「引導渡し」が行われます。
その後に行われるのが、会葬者による弔辞・弔電。弔辞は、故人と親交の深かった方が故人を弔う言葉なので、心当たりのある人がいたらぜひお願いしましょう。弔辞・弔電が終わると再び読経がはじまり、遺族、親族、参列者の順に焼香をします。焼香のやり方や回数は宗派によって異なるため、事前に作法を頭に入れておくと安心です。
読経が終わると僧侶が退場。司会者が閉会の辞を述べ、葬儀・告別式は閉式します。
火葬・散会

| 火葬・散会 | 出棺 |
| 火葬 | |
| 収骨(お骨上げ) | |
| 初七日法要 | |
| 精進落とし | |
| 散会・ご帰宅 |
出棺
葬儀・告別式の閉会後は、「お別れの儀」と呼ばれる出棺の準備に入ります。喪主や遺族、参列者で棺に花を入れ、故人と最後のお別れをしましょう。花や副葬品で周囲を飾ったあとは、棺のふたを釘でとめる「釘打ちの儀式」を行います。
釘打ちをしたら棺を霊柩車へ運び込み、喪主と遺族は別の車やマイクロバスで火葬場へ移動。火葬場に向かう人以外は、出棺のタイミングで解散します。
火葬
火葬場に到着したら、火葬炉の前で「納めの儀」を行います。お坊さんが読経したあと、最初に喪主、続いて遺族、親族、友人の順に焼香と合掌をします。
納めの儀が終わったら、そのまま棺は火葬炉へ。火葬は1〜2時間ほどかかるため、火葬場の待合室で待機しましょう。
収骨(お骨上げ)
火葬後は、遺骨を箸で拾い、骨壺に納める収骨(お骨上げ)を行います。骨上げの手順やマナーは地域によって違うため、火葬場のスタッフの指示に従うのが安心です。
初七日法要
初七日法要は、残された遺族が故人を追悼し、故人を供養するために行われる法事です。
本来は故人が亡くなった日から7日目に行いますが、最近は葬儀と同じ日に「繰り上げ初七日」として初七日法要を行うケースが増えています。火葬場から喪主と遺族がもどったら、初七日法要として僧侶に読経していただき、故人を供養するのが一般的です。
また、葬儀・告別式の最中に「式中初七日(繰り込み初七日)」として組み込む形式もあります。火葬の前後、どちらで行うかによって変わりますが、初七日法要の所要時間は15分~30分ほど。僧侶の読経後、親族や家族による焼香があり、最後に喪主が挨拶をして終わります。
精進落とし
精進落としとは、火葬または初七日法要後に設けられる会食のこと。葬儀の参列者や宗教者に料理をふるまい、感謝を伝える儀式です。食事の前に喪主が献杯の挨拶をし、食事の最中は遺族や喪主がお酌をして回ります。
とくに決まりはありませんが、精進落としは1~2時間で行うのが一般的です。食事のメニューは、お祝い事に使われる食材を避け、和食を中心に予算や規模にあわせて選べば問題ありません。
僧侶が会食に参加しない場合は、御膳料を包んで渡すのがマナー。お膳料の相場金額は5,000〜10,000円なので、封筒に入れてお渡ししてください。
散会・ご帰宅
精進落としの閉会をもって、葬儀は散会となり、参列者は帰宅します。最後に喪主から散会の挨拶を行い、僧侶や参列者に感謝の言葉を伝えましょう。
葬儀の終了後は、関係者へのお礼や相続の手続きなどを行わなければなりません。期限が設けられていたり、手順が難しかったりする手続きが多いため、抜け漏れがないよう注意してください。
葬儀後

| 葬儀後 | 関係者へのお礼 |
| 諸手続き | |
| 四十九日法要(忌明け法要) | |
| 納骨式 | |
| 香典返し |
関係者へのお礼
葬儀が終わり、落ち着いてきたら、関係者へ改めてご挨拶に伺います。親族だけでなく、ご近所や会社など、お世話になった方々へお礼を伝えてください。
事前にアポイントをとったり、手土産を持って行ったりすると丁寧でしょう。
諸手続き
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 葬儀費用の支払い | 葬儀社から請求書を受け取り、葬儀費用を支払う |
| 役所・銀行・保険の対応 | 年金の受給停止や預貯金の名義変更、生命保険の請求などを行う |
| 遺品整理 | 故人の遺品を整理し、家族や友人などに分配する |
| 遺産相続 | 故人の残した遺産を分割し、相続手続きを行う |
| 喪中の通知 | 亡くなった年の11月中旬~12月上旬に喪中はがきを送付する |
葬儀後は、葬儀費用の支払いだけでなく、行政・相続手続きを行わなければなりません。
期限の決まっている手続きもあるため、葬儀後は速やかに対応するのがベター。喪主が行うのが一般的ですが、家族や親族、専門家の手を借りるのもひとつの選択肢です。
四十九日法要(忌明け法要)
四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる儀式です。49日までを「忌中(きちゅう)」、49日以降を「忌明け(きあけ)」ということから、「忌明け法要」とも呼ばれています。
四十九日法要では、会式の挨拶のあと、僧侶の読経と焼香を行い、お斎(御斎・おとき)と呼ばれる会食をするのが一般的。また法要後に納骨式がある場合は、仏壇やお墓、本位牌を用意しておかなければなりません。
納骨式
納骨式とは、故人の遺骨をお墓に埋葬したり、納骨堂に納めたりする儀式。時期に明確な決まりはありませんが、四十九日法要とあわせて行うケースが多いです。
ちなみに最近は、お墓だけでなく、納骨場所が多様化しています。樹木を墓碑として遺骨を埋葬する樹木葬や、焼骨を海に散布する海洋葬(散骨)、遺骨の一部を自宅で保管する手元供養など、故人や家族の意向に沿った供養の方法を選べます。
香典返し
香典返しとは、通夜や葬儀・告別式、法要の参列者からいただいた香典に対して、お礼の品物をお返しすること。香典返しには、「無事に四十九日法要が終わりました」と関係者へ報告する意味が含まれています。四十九日法要の翌日から、遅くとも1か月以内に香典返しをするようにしましょう。
香典返しの相場は、受け取った金額の半分程度を返す「半返し(半分返し)」。地域によっては3分の1が通例だったり、高額な香典をいただいた方は4分の1にしたりと、臨機応変に対応して問題ありません。
葬儀・葬式を行う意味
葬儀の流れを確認したところで、最後に葬儀・葬式を行う意味について触れておきましょう。
日々の暮らしの中で、常に葬儀について考えている人はあまりいません。身内の方、または親しい方が亡くなってはじめて葬儀の準備をするのが一般的です。葬儀は故人を葬り供養するための儀式ですが、お葬式を行う意味はほかにもあります。
遺族の心の整理
身近な人が亡くなるのは非常に辛いため、事実を受け入れられない人も少なくありません。葬儀を行うことで、少しずつ現実を受け入れる方がほとんどでしょう。
故人の死を完全に受け入れるには時間がかかります。葬儀だけでなく、初七日や四十九日をはじめとした法要は、遺族が故人の死を受け入れ、心の整理をするための大切な仕組みです。
家族や親族のつながり
葬儀は、親せき同士で集まる数少ない機会のひとつです。近くに住んでいれば頻繁に会うかもしれませんが、遠方に住んでいる親せきと会う機会はほとんどないでしょう。
長期間会う機会がないと、関係が希薄になってしまいがちですが、葬儀や法要があることで結びつきを深められます。
宗教的な観点
葬儀には、死者を供養し、あの世へ送り出すという宗教的な意味があります。最近では、地域性や遺族の考え方によって、宗教的な意味合いがやや薄れているようです。
実は、明治時代にも葬儀から宗教的な意味を除こうとする傾向が強まっていました。その際に生まれたのが「告別式」。葬儀における宗教的な意味合いは、歴史のなかで濃くなったり薄くなったりを繰り返しています。
社会的な周知
葬儀は訃報を受けた人たちが集まり、故人が亡くなったことを認識するための儀式です。死亡届や遺産相続など、行政機関での手続きも行います。また、かつて地域のコミュニティーでは、葬儀を行うことで世代交代を知らしめる役割もありました。
葬式・葬儀をお考えの方はいい葬儀へ
一般的なお葬式の流れをまとめましたが、実際の葬儀では順番が前後したり、複数の作業を同時に行ったりすることがほとんど。また、大切な人を失った悲しみやショックを抱えながら葬儀の準備を進めるのは、想像以上に大変です。
葬儀の流れを頭に入れておきつつ、家族や葬儀社と相談しながら、状況にあわせて柔軟に対応するのが大切。万が一に備えて事前に葬儀社を選んだり、費用やプランを検討したりしておくと、満足いく葬儀をスムーズに実現できます。
いい葬儀では、24時間365日いつでも電話・メールで葬儀のご相談を受付中。葬儀前後の手続きや葬儀社の手配をサポートしますので、葬儀の準備を考えている方や急ぎで葬儀社をお探しの方は、ぜひいい葬儀にご相談ください。