 お葬式の全国調査
お葬式の全国調査 コロナ禍の喪主経験者への実態調査(2021年)/「コロナ対策は葬儀社への信頼度向上に重要だと思った」96.0%~葬儀のかたちは変わっても、故人を想い、見送りたい気持ちは変わらない~
終活関連サービスを提供する株式会社 鎌倉新書(東京都中央区、代表取締役社長COO 小林 史生、証券コード:6184、以下 当社)が運営する日本最大級の葬儀相談サイト「いい葬儀」は、2021年7月に「コロナ禍の喪主経験者に関する実態調査(20...
 お葬式の全国調査
お葬式の全国調査  お葬式ニュース
お葬式ニュース 新型コロナウイルスについて、喪主や遺族、参列者ができることについて、まとめました。なかなか人が集えない状況においても、故人とのお別れの場をきちんと用意したいという思いや、またそれに対する提案は日々、生まれています。こうした動きが、これからの日本の新しいお葬式や供養のあり方につながるかもしれません。
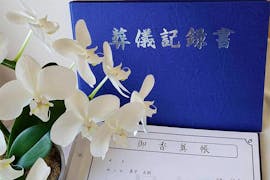 お葬式ニュース
お葬式ニュース 故人とゆっくりお別れする余裕がほしい。来てくれた方にきちんとお礼がしたい。そのような遺族の希望を叶える「葬儀受付代行サービス」が、東京都でスタートしました。親族や近所の方が行ってきた葬儀の受付や、現金の管理、記録書の作成を専門スタッフが代行してくれるという都内でも珍しいこのサービス。提供するのは株式会社ビットバイビット(本社:神奈川県相模原市)です。
 服装と身だしなみ
服装と身だしなみ 喪主はお葬式の主催者であるため、一般の参列者よりも特に服装や持ち物に気を払う必要があります。故人に恥ずかしい思いをさせないように、喪主の服装や持ち物について覚えておきましょう。ここでは、喪主に必要な服装、持ち物などを紹介しています。
 葬儀のマナー
葬儀のマナー  お布施
お布施  葬儀の流れ
葬儀の流れ  お布施
お布施  葬儀の費用相場
葬儀の費用相場  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀・仏事の知識
葬儀・仏事の知識  葬儀の費用相場
葬儀の費用相場  法事・法要
法事・法要  葬儀のマナー
葬儀のマナー  葬儀のマナー
葬儀のマナー 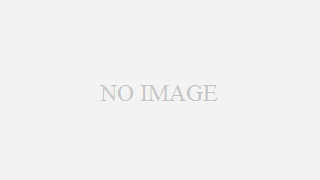 市川愛の「教えて!」お葬式
市川愛の「教えて!」お葬式 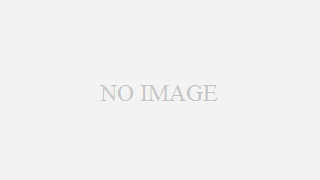 市川愛の「教えて!」お葬式
市川愛の「教えて!」お葬式