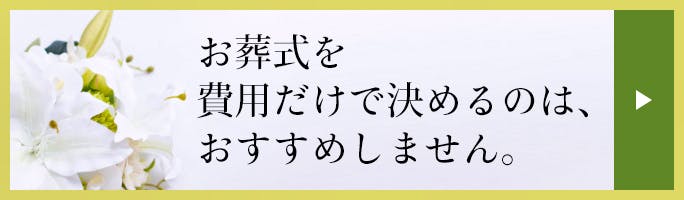葬儀を執り行う上で、多くの人が頭を悩ますのは費用の問題ではないでしょうか。
大切な家族をしっかりと見送りたい気持ちはあるもののすぐ用意できるお金に限りがあったり、故人からも「簡素な葬儀で良い」と頼まれることも。葬儀の規模やかたちも多様化している昨今、「豪華な葬儀だから良い」とも限りません。
この記事では、葬儀費用をおさえるポイントや、葬儀費用の相場、費用をおさえた場合の注意点などをご紹介していきます。
目次
葬儀費用を安くおさえるための7つの方法
葬儀費用を低額でおさえるためのポイントはいくつかありますが、ここでは比較的実行しやすい7つの方法をご紹介します。
- 複数社から見積りを取って比較検討する
- 葬儀の規模をおさえる
- 葬儀プランを見直す
- 市民葬・区民葬を利用する
- 福祉葬を利用する
- 補助や扶助制度を利用する
- 葬儀保険に加入しておく
①複数社から見積りを取って比較する

複数の葬儀会社から見積りをもらい、それぞれを比較検討する方法です。
初めに自分がどのような葬儀を希望するかを伝えると、それを実現するための見積りを出してもらいます。
どれくらいの価格で自分の希望が実現するのかという相場感を把握できますし、何にどのくらいお金がかかるかを知ることで削るべきポイントを見極めることもできます。
ただし、比較検討に時間がかかるので、早く葬儀を行いたいときには不向きな方法です。
②葬儀の規模をおさえる
単純に葬儀の規模を小さくしてコストを下げる方法です。会場を小さめのところにしたり、料理のグレードをおさえたりすると価格に反映されやすいです。
しかしあまり規模をおさえすぎると、親族や参列者などから不満が出る可能性があります。
③葬儀プランを見直す

葬儀費用の内訳には、葬儀そのものの費用、接待や返礼品にかかる費用、宗教者に渡すお布施の3つに分けられます。そのうち、葬儀にかかる費用を見直すことで葬儀費用をおさえることができます。
最初に葬儀社に提案されたプランを見直し、詳しい内訳を見ると不必要なサービスや数量が多いものもあります。
式場使用料、祭壇の種類、料理のランクなどは選んだものによって変わってきます。祭壇など幅広く料金設定があるものは最後に選ぶと良いでしょう。
④市民葬・区民葬を使う
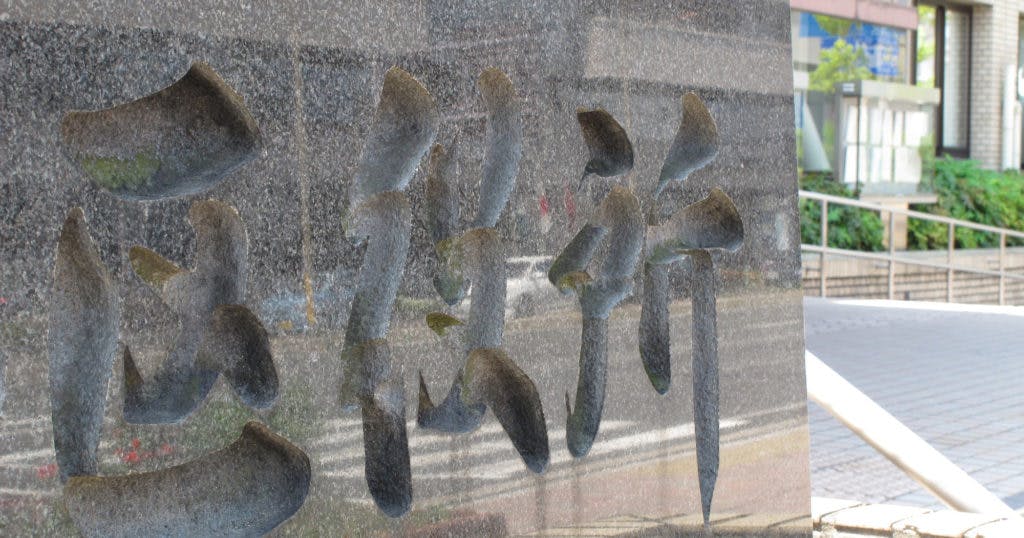
市民葬(区民葬)とは、市、区の自治体と葬儀社が連携して行う葬儀を言い、直接葬儀社に依頼するよりも安い価格で葬儀ができる制度です。
これら市民葬や区民葬など、自治体が行っているお葬式サービスを利用すると、コストを安くおさえられます。
自治体に市民葬を申し込むと、自治体と提携している葬儀会社が葬儀を行ってくれます。自治体の基準を満たした葬儀会社がお葬式を行ってくれるので、一定の安心感があります。
一方、原則的にその自治体の住民しか利用できないのが難点です。
葬儀費用は基本的に低額ですが、市民葬の料金に含まれているものの内容(プランの内容)は、各自治体によって異なります。基本メニュー以外のことをするには追加費用が発生することもデメリットといえます。
⑤福祉葬を利用する
「福祉葬」とは、生活保護法第18条に基づいて、葬祭扶助によって行われる葬儀のことを言います。生活保護を受けている世帯の方が亡くなり、葬儀費用を出せない場合に適用されます。
葬儀にかかる費用を支給されるのがメリットですが、対象となる人は限られます。
葬祭扶助で支給される費用は、搬送、火葬、納骨など最低限です。僧侶による読経や戒名の授与など宗教的な儀式はありません。
⑥補助や扶助制度を利用する

葬儀終了後に遺族が手続きを行うことで、故人が加入していた保険や組合から葬祭費用の給付金を受け取れる制度があります。
例えば、故人が国民健康保険に加入している場合、3万~5万円程度の葬祭費の受け取りが可能です。また、健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。これは対象者が加入している保険の種類によって、もらえる補助金が変わってきます。
これらは申告しないともらえないので、忘れないよう注意が必要です。また葬祭費、埋葬料の申請は死亡から2年以内までと期限が決められています。
⑦葬儀保険に加入しておく
葬儀にかかる費用をあらかじめ少しずつ用意できるのが「葬儀保険」です。各保険会社が葬儀費用のための葬儀保険のプランを用意しています。
葬儀保険は月々数百円から積み立てられる少額保険であり、高齢の人でも加入しやすいことがメリットと言えます。また、契約者が死亡した場合速やかに保険金が降りることも利点と言えるでしょう。
一方、基本的に掛け捨ての保険なので解約時にお金が戻ってこないこと、保険会社が倒産した時の補償がないのがデメリットと言えるでしょう。
葬儀費用を“後から工面”する3つの裏ワザ
裏ワザというほどでもありませんが、後払いにするための方法が3つあります。
- 葬儀ローンを活用する
- お香典でまかなう
- 遺産相続で支払う
葬儀の費用はとかく高額になりがちです。今、手元に高額のお金がなかったとしても、上記のような方法をとれば、葬儀費用を工面する(もしくは補填する)ことができるでしょう。
①葬儀ローンを活用する
葬儀ローンとは、葬儀費用の支払いについて分割払いができる金融サービスです。葬儀後にどうしても料金が払えない場合に検討しても良いでしょう。
ローンですから手数料はかかりますが、一時的な金銭の支出がおさえられること、予算を越えた葬儀ができるのは利点と言えるでしょう。
ただし、葬儀ローンは審査に通らないと利用できません。審査は年齢、職業、勤務年数、年収、既存の借入の有無や残高などをもとに行われます。即日で結果が出るところもありますが、葬儀ローンを利用する機関によって審査基準が変わる場合もあります。
②お香典でまかなう

葬儀に参列者を招いた場合、故人への気持ちとして香典を受け取れることができます。お香典の額は参列者の人数によるため、もしかしたら参列者を多く招いたほうがお香典で相殺できるかもしれません。
しかし、実際もらったお香典の半額くらいはその3分の1から半分程度の額を香典返しとして会葬者に返すことになります。そのため、手元に残るのは半分程度と思ったほうが良いでしょう。
また、何人参列に来るかも葬儀当日にならないとわからないため、いくらもらえるかの予想が立てにくいです。
直葬のようなほぼ親族だけの葬儀ではお香典が見込めないので、ほぼ全額負担となります。
③遺産相続で支払う

葬儀費用を支払う人が相続人の場合、相続財産から支払うことが可能です。
さらに、相続財産から葬儀費用を支払うことで、支払った分だけ相続財産から差し引いて相続税の計算ができます。そのため、相続税対策にも繋がります。
しかし、葬祭費用として相続財産から差し引けるもの、差し引けないものがあるので注意が必要です。
相続財産から差し引けないものは「香典返しにかかった費用、墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるためにかかった費用、初七日や四十九日法要などにかかった費用」です。それ以外のものは差し引けると考えましょう。
相続税の申告は故人が死亡した日から10か月以内です。相続税申告書や必要書類のほか、葬儀社からの領収証を持って所轄の税務署に提出します。
ちなみに、葬儀費用は確定申告の対象外です。また、お香典は非課税のため、確定申告の必要はありません。
葬儀形態ごとの費用相場

葬儀費用の相場は地域や葬儀の規模、葬儀形態によって異なります。
葬儀は大きく分けて「一般葬」「家族葬」「一日葬」「直葬」の4つに分けることができます。その中でも費用をおさえられやすい家族葬・一日葬・直葬(火葬式)について、少し詳しくみていきましょう。
家族葬

家族葬の平均費用は約96万円ほどです。
葬儀の規模としては小さいですが、行うことは一般葬と変わりません。参列人数が限られるため接待や返礼品の費用がおさえられるのがメリットです。
本来は家族だけで行う葬儀を家族葬といいますが、現在では家族に加えて親戚や親しい友人知人を混じえて行う小規模な葬儀のことを一般的に家族葬と呼びます。
小規模とはいえお通夜と告別式を行う点は一般葬と同じです。
一日葬
一日葬の平均費用は約85万円。一日葬は葬儀費用を節約できる葬儀の種類のひとつです。
お通夜を行わず、葬儀・告別式、火葬のみ行います。通夜を行わないため通夜料理を節約することができます。また、通夜で遺族が弔問客の対応に追われることもなく、身体的な負担も軽減することができます。
1日しか会場を使わないので会場費が半分になると思う人が多いのですが、前日からの準備で会場を占有することになるため、半額になるわけではありません。
また、遠方から参列する親族の宿泊費を家族が負担するようであれば、その宿泊費もおさえることができます。
一日葬は葬儀にかかる時間と費用をおさえたシンプルな葬儀ですが、その人らしく見送れるのがメリットと言えるでしょう。
直葬(火葬)
火葬式・直葬にかかる費用の平均は45万円程と、かなり費用をおさえられる葬儀のひとつです。
火葬式・直葬はもっともシンプルな葬儀の種類。火葬場に集合・解散します。希望により宗教者に読経をしてもらうこともでき、焼香を済ませるとすぐ火葬に入ります。
先ほど紹介した一日葬、家族葬より葬儀費用をおさえられるのが最大のメリットと言えます。参列者の人数もごく少数に限られるため、葬儀の規模としても小さいです。
その一方デメリットもあり、葬儀にかかる時間が極端に短いため、故人を見送ったという実感が持てなかったり、気持ちの整理がつかないという人も。
また、一日葬と同じく新しい葬儀の種類のため、菩提寺の許可が必要になることも。相談せずに火葬式・直葬を行った場合、納骨を断られることもあります。
もっとも安い直葬のメリットデメリット

直葬はもっともリーズナブルな葬儀形態ですが、良い点と悪い点があります。
メリット1 時間がかからない
直葬では通夜や告別式を行いません。このため、短い時間で葬儀を終えることができます。直葬の場合、臨終から遺体を24時間以上安置した後、納棺し、火葬場へ出発することになります。
1~2時間程度して火葬が終わったら骨上げを行い、それが終われば基本的には解散です。地域差はあるものの、大体以上の流れで終わります。
短い時間で終わるということは、長時間の葬儀が辛い高齢者や障害者の方、妊婦の方などの負担が軽くなるということです。
メリット2 手続きが簡単
通常の葬儀では、日程と会場の決定、葬儀の流れの決定に始まり、弔問客の受付方法、細かい部分では会食時のメニューや式の間に流す曲などさまざまなことを考えなくてはいけません。
しかし直葬は通常の葬儀と違ってシンプルなので、考えることはそう多くありません。
葬儀自体は地味かもしれませんが、雑事にとらわれず心から故人の死を悼む余裕が生まれます。
メリット3 弔問客の対応に追われづらい
直葬の場合、火葬までの間は親族のみで過ごすことが多くなります。弔問客が来たとしても、人数は少ないことが大半です。
直葬にすればたくさんの弔問客の対応に追われることはほとんどありません。
デメリット1 見送った実感がわかない
直葬は一般的なお葬式に比べるとあっという間に終わります。あまりにもあっさりしているので、見送った実感がわかなかったという声もあります。
デメリット2 故人の友人、知人とトラブルになることも
お葬式は故人との最後の別れの場です。親しい人であれば、しっかりとお葬式に参加して見送りたいと思うのが普通といえます。
しかし直葬はお通夜や告別式のないシンプルな葬儀であり、参列者が家族親族のみというケースが大半です。
あまりに簡素な式のため、故人に親しい人から「ちゃんと送ってあげないなんて」などの苦情が発生し、トラブルに発展するおそれもあります。
しっかりと事情を説明すればわかってもらえることも多いので、あらかじめ説明の方法を考えておくといいでしょう。
デメリット3 業者の対応がずさんなケースもある
直葬は葬儀社にとって利益の薄い葬儀形態です。このため、簡略化とコストダウンが図られることが多くなっています。
結果的に業者から満足な対応を受けられないケースもあります。直葬とはいえ、できるだけ評判のいい業者を選ぶことが大切です。
エリアから火葬式(直葬)の費用/最安価格を調べる
日本最大級の葬儀相談・依頼サイト「いい葬儀」では、火葬式(直葬)ができる葬儀社のプラン最安価格を掲載中。予算やご要望に合った葬儀社をご案内します。
火葬場にもよりますが、平均的に10万円〜40万円前後が多いようです。
(例)東京:82,999円〜大阪 77,000円〜)
ネットで見かける安価な定額プランの実態
インターネットで安い葬儀業者を探すと、相場よりも安い金額を提示している業者が数多く検索にヒットします。
定額プランといって、追加料金が発生しないことをセールスポイントにしている業者も多いようです。では、定額プランの実態とはどのようなものなのでしょうか?
事前に葬儀会社を選べない

定額プランの多くは、仲介している業者が、提携している葬儀社を各顧客に割り振る形で運営されています。
葬儀社は空き時間を利用できるのでメリットになりますし、顧客はすぐに葬儀をあげてもらえるのでメリットになります。仲介業者は仲介料をもらえるので、やはりメリットになります。
しかし事前に葬儀会社を選べないので、希望している会社がある場合は不満が残るかもしれません。
定額としながら実は追加料金がかかるプランが多い
ネットで見かけるお葬式の定額プランには、どちらかというとお葬式のセットメニューとなっているものが多いようです。
実際に、祭壇の設営費・会場費・棺の代金などがセットとして定額になっているものが多く見受けられます。
一方で、定額セットの内容に僧侶へのお布施や会食の代金などが含まれていないものもあり、定額とはいいながら必要に応じて追加料金が発生するプランが大半のようです。
定額プランを検討するときは、定額で何ができるのかをしっかりと押さえてください。
定額にするには制限を守る必要があるプランも多い
ネットで見かけるお葬式の定額プランには、「ここまでは定額だけど、これ以上は追加料金」というシステムが内包されているものが散見されます。
例えば「霊柩車の走行距離が一定距離を超えると追加料金が発生する」といったタイプのプランがこれにあたります。
こういった定額プランは何かにつけて追加費用が発生します。結果的に想定していた額以上のお金を支払うことになるかもしれません。
葬儀費用はお香典で相殺できる?

香典の額は地域による違いや故人との関係性による差異が大きいのですが、1回の葬儀で喪主側が受け取る香典の総額を平均した場合、70万円程度になるとされています。
既に述べた葬儀費用と比べると、香典でその多くを賄うことができるとも考えられます。
しかし香典を受け取った場合、香典額の3分の1から半分程度の額を「香典返し」として参列者にお返しすることになります。仮に3分の1を返した場合、手元に残る香典は50万円弱です。
一般葬以外の葬儀形態では、基本的に参列者の数が少ないため香典の額も少なくなります。特に参列者の少ない直葬の場合、ほぼ香典収入を見込めないので、葬儀を出した家が全額負担となるケースが大半です。
以上のことから、香典で葬儀費用全額を相殺することは難しいと考えられます。もちろん香典で葬儀費用の一部を相殺することは可能です。
しかし葬儀でいくら香典を集められるかは、実際に葬儀を行ってみないとわかりません。香典で葬儀費用を賄えると見込んで高額な葬儀を行うことは避けた方がいいでしょう。