九戸郡九戸村 (岩手県) で葬儀社をお探しの方へ/家族葬のご案内を2件掲載
早朝・深夜も搬送可能
相談無料・24時間365日
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
病院から今すぐ搬送したい
相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
九戸郡九戸村の葬儀社一覧
1~2件目 / 2件
お迎え対応エリア:九戸郡九戸村・九戸郡洋野町・九戸郡野田村・九戸郡軽米町・三戸郡新郷村・三戸郡階上町・三戸郡南部町・三戸郡田子町・三戸郡五戸町・三戸郡三戸町・上北郡おいらせ町・上北郡六ヶ所村・上北郡東北町・上北郡横浜町・上北郡六戸町・上北郡七戸町・上北郡野辺地町・三沢市・十和田市・八戸市
もっと見る- 評判の良い葬儀社
- 家族葬 対応可
- 直葬
- 火葬式 対応可
- 一日葬 対応可
病院から今すぐ搬送したい
相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
病院から今すぐ搬送したい
早朝・深夜も搬送可能
相談無料・24時間365日
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
家族葬とは/費用相場と葬儀の流れ
家族葬とは、家族や親せき、故人とごく親しかった人などが参列するお葬式のことを言い、「喪主が、参列する人を選べる(招待できる)」という特徴があります。葬儀費用を安く抑えたい場合に、招待する人を限定した小規模な家族葬が選ばれることも多いです。参列人数を事前に決められるため、用意する食事や香典返し・返礼品に関して余分を考える必要がなく、結果的に費用を抑えられるのです。
家族葬の費用相場※
| 全国平均 | もっとも多い価格帯 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 72万円 | 40万円以上~60万円未満 |
| 飲食費 | 17万1千円 | 0円~5万円未満 |
| 返礼品 | 16万5千円 | 0円~5万円未満 |
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)
岩手県での家族葬の流れ
1日目
納棺・通夜

納棺の儀では、故人の旅立ちを迎えるために身仕度を整え、愛用の衣類や思い出の品を柩におさめます。納棺を済ませたら、通夜式を行います。読経・焼香の後、喪主または親族代表が挨拶をし、お清め料理などで弔問客をもてなします(通夜振る舞い)。
2日目
葬儀・告別式

葬儀斎場にて、読経・焼香、弔辞・弔電、お別れの儀式といった流れで葬儀・告別式を執り行います。
出棺:故人と最後のお別れの儀式です。故人をお花で飾り(別れ花)、別れのときを過ごした後、近親者で棺を霊柩車に納め、火葬場へ向かいます。
火葬: 火葬場へ到着したら、火葬許可証を提示し、火葬を執り行ないます。ご遺族お立会いのもと点火が行われ、棺を炉の中に納めた後、喪主の方から順に焼香を行います。火葬後は係員の指示に従い、お骨上げを行います。3日目
初七日・百か日法要(繰り上げ法要)

火葬の後、初七日・百か日法要を兼ねて精進落としを行います。精進落としの席では、食事やお酒、茶菓子などでお世話になった方々の労をねぎらいます。
葬儀終了後:自宅に戻って後飾り祭壇を設置し、ご遺骨・位牌・遺影を安置します。なお、白木の位牌は、忌明けの法要時に本位牌に入魂して取り替えます。
葬儀形態の特徴
葬儀の種類別、葬儀費用の目安※
| 葬儀の種類 | 全国平均 | もっとも多い価格帯 |
|---|---|---|
| 直葬・火葬式 | 42万8千円 | 20万円以上~40万円未満 |
| 一日葬 | 87万5千円 | 20万円以上~40万円未満 |
| 家族葬 | 105万7千円 | 60万円以上~80万円未満 |
| 一般葬 | 161万3千円 | 120万円以上〜140万円未満 |
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)
家族葬(かぞくそう)

家族葬とは、家族や親族、故人と親しかった人が参列し、故人とのお別れの時間を 大切にしたお葬式です。 葬儀の内容や流れは通常の葬儀と大きな違いはありません。 人数が特に決まっているわけではありませんが、5〜30名程度で執り行われる場合が 多いようです。
一日葬(いちにちそう)

通夜をおこなわず、葬儀・告別式のみを一日で行います。 遠方に暮らす親戚や、高齢者が多いなどの理由があっても、短い時間できちんと したお別れができます。 一般的に正午あたりからお葬式を開始することが多く、通常の葬儀同様精進落とし を振る舞うこともあります。
火葬式(かそうしき)

宗教的な儀式などを省き、火葬をメインとしたお葬式です。 ご希望により、火葬場の別室や仮装炉の前などで故人との簡単なお別れの場を 設けることもあります。 故人に近しい、ごく限られた参列者のみで簡潔なお別れをします。
都道府県別の葬儀費用
岩手県の葬儀費用相場
お葬式の費用内訳は、お葬式そのものにかかる費用、飲食費、返礼品、お布施に分けられます。
約105万8千円※(参列人数28名)
上記金額に含まれる内容
お葬式費用
60万5千円
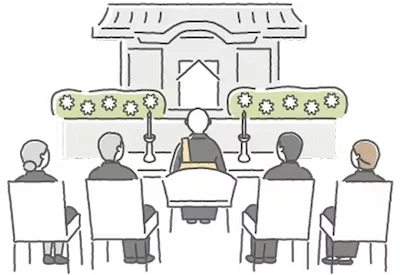
- 火葬場費用
- 式場費用
- 運営スタッフなど
飲食費
22万7千円
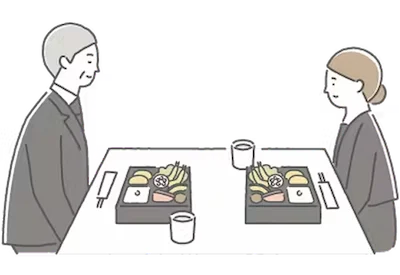
- 通夜振る舞い
- 精進料理
- 飲み物など
返礼品
22万5千円
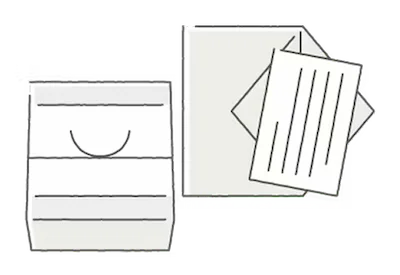
- 会葬者への返礼品
- 香典返しなど
岩手県の葬儀・葬式事情
日本最大級の葬儀相談・依頼サイト「いい葬儀」では、岩手県での葬儀を依頼できる、当地での実績豊富な葬儀社をご紹介します。
火葬式、一日葬、家族葬、密葬など、人気のプランを紹介するとともに、お客様の状況に合わせたご提案と葬儀社選びのサポートをします。また、葬儀・葬式・家族葬の費用、口コミ、葬儀事例、担当スタッフなどの情報も掲載しています。
近隣病院からの移動が必要なお客様には、お近くで安置施設のある葬儀場・斎場や即時対応できる葬儀社をご案内しますので、深夜・早朝を問わずいつでもご相談ください。
岩手県の葬儀の風習
出棺の際に持たせる副葬品の一つとして、全国的には六文銭を利用することが多いものです。火葬ではお金や金属など燃えないものを入れるわけにもいかず、紙に一文銭を6つ印刷したものを入れるというのが一般的です。これは、三途の川を渡る時の渡り賃として、またあの世に行ってもお金に不自由しないようにという思いがつまったものです。
岩手県では、六文銭を入れるのではなく現代的な金額が紙に記入されて持たせられます。100万円と記入することが多いのですが、中には1000万円や1億円など高額な金額を記入されることもあります。
岩手県の葬儀の流れ
岩手県では、逝去から葬儀式までにある程度の時間をおくのが一般的であり、3日から5日ほどの期間を確保し、葬儀の前日だけでなく逝去から葬儀までの毎日を通夜として毎晩供養の念仏が行われています。また、通夜の後にも招待された近親者のみで行われるお逮夜と呼ばれる儀式があり、再び通夜が行われています。
葬儀では骨葬で行うのが岩手県では一般的であり、先に火葬を済ませておき、地域によっては骨壺に入れずにそのまま自宅へ持ち帰るところもあります。葬儀では、親族が先に会場に向かって参列者を迎えるというのが全国的に行われている風習ですが、岩手県では最後に親族と僧侶が入場するということもあります。
みんなが選んだ葬儀形態(岩手県)
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)
岩手県で41.2%と家族葬を選ぶ人が多いようです。その他の葬儀形態は、一般葬29.4%、直葬・火葬式17.6%、一日葬11.8%となります。
想定費用と実際の費用のギャップ(岩手県)
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)
葬儀社を決めた理由(岩手県)
- 1
葬儀業者の会員だったから
- 2
その葬儀業者を過去利用したことがあるから
- 3
予算に見合った費用だったから
葬儀担当者の対応がよかったから
信頼できる人(親戚・友人知人など)の紹介だったから
葬儀社について後悔していること岩手県)
- 1
複数の葬儀業者を比較しなかったこと
- 2
優良な葬儀業者がわからなかったこと
意図しない追加料金があったこと
参列者からのお香典平均総額(岩手県)
約39万3千円(参列人数28名)
九戸郡九戸村の葬儀場・斎場でよくある質問
葬儀社選びに関して注意する点を教えてください。
第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)によると、葬儀業社選びについて後悔したことは、複数の葬儀業者を比較しなかったこと、意図しない追加料金があったこと、葬儀における不明点を明確にできなかったこととなっています。
このような事態を避けるためにも、時間と気持ちに余裕があるうちに事前の準備をしておくことをおすすめします。九戸郡九戸村で実績のある葬儀社・葬儀屋を教えてください。
九戸郡九戸村の葬儀・家族葬で実績のある葬儀社は、有限会社中野葬具仏具店、株式会社山村陽一葬儀店などがございます。
日本最大級の葬儀相談・依頼サイト「いい葬儀」では、九戸郡九戸村で葬儀・家族葬ができる葬儀社を2件掲載!口コミ評価のほか散骨対応といった条件や、施行実績で定評のある葬儀社ランキングや詳細条件から最適な葬儀社をお選びいただけます。
九戸郡九戸村の葬儀社一覧九戸郡九戸村の葬儀・家族葬の料金、費用目安を教えてください。
九戸郡九戸村での葬儀・家族葬にかかる費用は対応する葬儀社やプランによって異なります。「いい葬儀」では、九戸郡九戸村の各種葬儀プランをご用意。お客様のご希望に合わせたプランをご提案しています。
九戸郡九戸村で葬儀・家族葬を行う流れを教えてください。
九戸郡九戸村での葬儀・家族葬について、「いい葬儀」では下記の流れでご案内いたします。
STEP1:まずはお電話ください
お客様のご状況に合わせてご案内いたします。最初のお電話にて以下の情報をお知らせいただけますとスムーズです。
・お電話されている方の氏名と連絡先
・故人様のお名前と続柄
・故人様の居場所(ご自宅、病院、警察署など)STEP2:葬儀社をご紹介
お客様のご希望をお伺いしたうえで最適な葬儀社をご紹介します。
病院・警察からの移動が必要な場合は、葬儀担当者がすぐにお迎えにあがります。
※万一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能です。STEP3:搬送・安置
葬儀担当者がご指定の安置場所までお送りします。
STEP4:葬儀のお打ち合わせ
ご安置が終わりましたら、葬儀社との打ち合わせを行います。
お打ち合わせでは、葬儀の日程、プランやお見積もり金額の確認、お坊さんの手配などを決めていきます。
ご契約の前に、サービス内容や金額など納得いくまでお話されることをおすすめします。STEP5:葬儀施行
故人様との最後のお別れの場となります。
葬儀の専門スタッフがすべて手配いたしますので、安心してお任せください。葬儀・家族葬に関する情報はどこで手に入りますか?
「いい葬儀」では、お葬式をはじめ、お墓・仏壇・相続など、終活で必要となる知識や情報を「はじめてのお葬式ガイド」という形で提供しています。以下では、お客様の状況ごとによく読まれている記事をご紹介します。
葬儀の準備・進行



病院から今すぐ搬送したい