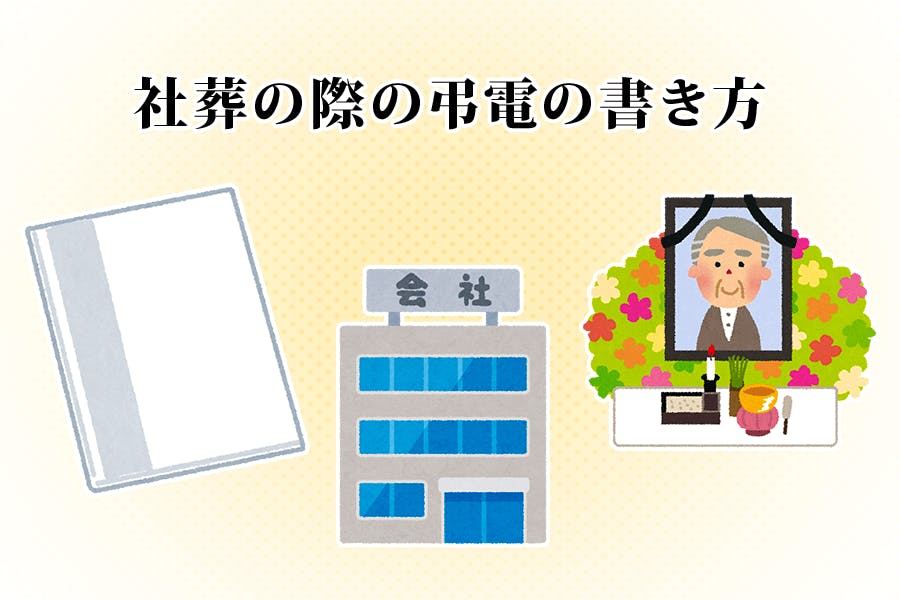弔電とは、故人や遺族に対するお悔やみの電報です。一般的には通夜や葬儀に参列してお悔やみを伝えますが、参列できない場合には弔電を送ります。弔電は、故人の遺族に送るものもあれば施主である会社に送るものもあります。
これまでに個人で弔電を送ったことがあるものの会社宛てにはないという方や、そもそも弔電を一度も送ったことがないという方もおられるかもしれません。社葬の弔電は個人葬のものとは異なるため、覚えておくべきルールやマナー、書き方の注意点も多くあります。ここでは社葬の際の弔電の書き方、送り先、差出人、送り方などについてご紹介します。
社葬で弔電を送る際に覚えておきたいこと
弔電の送り先と受取人、差出人

社葬の弔電を送る際に覚えておきたいのは、弔電の送り先と受取人です。個人葬であれば遺族が喪主となるために送り先は喪主となりますが、社葬では主催者を事前に確認しておく必要があります。
宛名は、葬儀を会社で行うか遺族で行うかによって変わります。
企業や団体が主催する際には、宛名を会社名や部署名にします。遺族で行うときには、喪主や特定の個人に向けて送るようにします。
社葬の案内状や通知の中に、弔電の受付に関する記載がされていることがあるので、あらかじめ確認し、記載がない場合は先方に問い合わせる必要があります。
社葬の責任者が不明な場合は「〇〇会社 故〇〇〇〇 葬儀責任者様」など、個人名を書かずに送ることもできます。
弔電の文末には、差出人の名前を記載します。個人葬では差し出す本人の名前にするのが一般的ですが、社葬では名前は自分の会社名に加えて、自分の会社の社長名も併せて記載する必要があります。なぜなら、弔電は最終的には遺族に渡される場合が多く、会社名だけだと誰からの弔電なのかがわからず、遺族がお礼状を出す際に困ってしまうことがあるためです。
差し出す側の会社内で話し合って事業所長や支店長などの実務担当者を差出人にすることもあります。重要な取引先には、社長名のものと担当者名のもので2通出すこともあるようです。
また、故人と特別な親交があった場合には、個人的に弔電を送っても良いでしょう。
弔電の送り方
一般的に、弔電は葬儀や告別式の前日までに打ちます。社葬の日時が前もって決まっている場合には、期日を指定することもできます。弔電を受け付けているNTTの場合、弔電の受付時間は午前8時~午後7時までで、全国どこでも当日の配達となります。

弔電の受取人や差出人が所属する会社名や肩書を記載する場合、メッセージ本文には正式な名称を書くのが一般的です。しかし長すぎる場合は、失礼にならない範囲で略しても問題ありません。
一方で、送り状の宛名や差出人については、主に配送に利用される情報なので、必ずしも正式名称などで書かなくても大丈夫です。配送員や受け取った方がわかる範囲で省略しても問題はありません。
社葬の弔電の書き方、文例と注意点

お世話になった故人が勤めていた会社であることから、本来であれば通夜や葬儀に参列してお悔やみの気持ちを伝えるのが望ましい形ですが、突然の訃報の場合は都合によって参列できないということもあります。そのような場合には、弔電でお悔やみを伝えることになります。
弔電には、さまざまな例文が用意されています。書き方に悩んだ場合は参考にするとよいでしょう。
- 〇〇会長のご逝去を悼み、心からお悔やみ申し上げます。
- 貴社専務の〇〇氏、ご急逝の知らせを受け、心より哀悼の意を表します。
- 〇〇専務の突然の訃報に、深く悲しんでおります。謹んでお悔やみ申し上げます。
- 貴社の〇〇様のご永眠に接し、深く哀悼の意を表します。
- ご逝去を悼み、故人のご功績をたたえ、心からお悔やみ申しあげます。
- 会長様ご天寿を全うされました由、謹んで哀悼の意を表します。
- 〇〇様の不慮のご逝去の報に接し、貴社ご一同に心からお悔やみ申しあげます。
- 御社〇〇様のご生前の功績をしのび、当社幹部一同、心からご冥福をお祈り申しあげます。
- 突然のご逝去に接し、職場の一同、まことに驚愕、くやしさで言葉もありません。深く哀悼の意を表わします。
- 〇〇社長の突然のご逝去に接し、職場の一同、言葉もございません。深く哀悼の意を表します。
- 御社会長の片腕として、永年ご活躍されてきた専務〇〇氏、突然のご永眠、言葉もございません、遥かに、哀悼の意を表します。
- 貴法人〇〇様の生前の偉大なご功績に尊敬の念を持って、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
- かねてご病気、ご療養中とは伺っておりましたが、このたびの〇〇会長のご逝去の報に、心からお悔み申しあげます。
- 〇〇翁の突然の訃報に、家内ともども深く悲しん でおります、このくやしさを仕事にぶつけ精進いたす所存です。
- 天寿を全うされました〇〇会長の、在りし日を偲びつつ、ご冥福をお祈り申しあげます。
- 貴社〇〇氏の、ご逝去のご通知をいただき、心からお悔やみ申しあげます。
- 御社会長のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。
- 在りし日のすばらしい社長を偲び、はるかにご冥福をお祈り申しあげます。
お悔やみの言葉は上記の例文のような定型文でも問題ありませんが、故人を偲ぶという観点から例文に頼らずに、自身の言葉を送ることも大切です。
弔電を打つ際には、いくつか注意点もあります。例えば、「忌み言葉を避ける」「相手の事情に深く立ち入らない」「くだけた文体にしない」などです。書き方に不安がある場合には、定型文を利用するとよいでしょう。弔電の奉読時間は3~4分が目安とされています。そのため、短すぎるものや長すぎるものは避けましょう。文字数の目安としては1,000文字程度が理想といえます。先方から弔辞を依頼された場合には、断る明確な理由がない限りは引き受けるのが一般的です。
社葬での供花、供物の送り方
社葬の案内状や死亡広告には、供花・供物を辞退する意向が示されている場合があります。その理由として、会場に設置される供花の配列の順番にトラブルが起こる可能性があること、スペース上の問題、まちまちの供花が届けられた場合に外見上不揃いとなってしまうこと、などという問題があります。
供花・供物を辞退する意向が示されている場合は、その意向に従い、供花・供物を送らないようにしましょう。特に意向が示されていない場合は、必ず問い合わせて、確認することが大切です。
供花を送る場合は、供花の種類や札の大きさが揃い、あらかじめ供花の数の予測がつくことから、「供花料」を送り、先方に依頼するほうが喜ばれることもあるため、その点も必ず確認しましょう。
社葬では、供花・供物は故人や遺族と親しい人が個人的に送ることが多く、企業や団体が送るのは花環が一般的ですし、供花の場合は、式場の大きさによって飾ることができないケースや、飾る時間に制限があり、届いたときには飾れない場合もあります。さらに、宗派によって花の色や種類が決まっていることもあり、会社によっては、供花・供物は一括して注文しようと考えている場合もあります。
問い合わせた結果、「一括して注文している」と言われたときは遠慮することなく依頼し、「供花料」を送ります。一括注文する予定もなく、辞退もしていない場合は、自社で業者へ手配します。
最近は、花祭壇が主流となっているため、いただいた供花代を花祭壇の設置費用に含める場合もあります。その場合は、供花芳名板に供花をいただいた方の名前を記すことがあります。
供花について断り書きがない場合は、送り先の意向を確認することが必要です。企業によっては、送っていただける意向のみを確認し、見栄えをよくするために供花を一括して注文する場合がありますので、その場合は供花料を贈ります。
供花は、本来は自分の手で霊前に供えるものですが、現状では業者や生花店に依頼し、会場へ届けてもらうことが通常となっています。
そもそも社葬とは?個人葬との違い
施主が違う
社葬は、会社をあげて故人を弔う葬儀です。
社葬の対象となるのは、会社の創業者や現職の重役、または会社の発展に大きく貢献した従業員、もしくは職務中に事故などで殉職した従業員などです。
個人の葬儀と社葬にはいくつかの違いがあります。
まず、最も大きな違いのひとつが施主が企業であるということです。
施主とは、本来はお布施をする人のことです。今ではお葬式や法事、法要などを行う主人となる人。簡単に言ってしまえば、費用を出す人を指します。
家族葬など遺族が行う個人のお葬式の場合は、弔問を受ける葬儀主催者である喪主と、葬儀費用の負担者であり運営の責任者でもある施主が同一人物であるというのが一般的です。
一方、社葬の場合は喪主と施主が異なり、遺族が喪主を務め、会社が施主を務めるというのが一般的です。
個人葬では、故人の配偶者や長男が施主と喪主の両方を務めることが多くなっています。社葬では施主を会社が務めますが、対外的な代表者として社長などが務める葬儀委員長が選定されます。
葬儀のメインの目的が違う
個人葬と社葬の違いは、その目的にもあります。
個人葬が故人を哀悼し、慰霊することを主な目的としているのに対して、社葬ではそれらに加え、故人が会社で成し遂げた偉業にも触れ、今後の体制に不安がないことを伝えるという目的があります。
これにより会社は結束し、社内の体制がより強固になることが期待されます。個人葬ではこうした側面はありませんが、社葬では会社の信頼性の高さを社内外に伝えることで、その後の経済活動をより円滑なものにするという側面が含まれています。