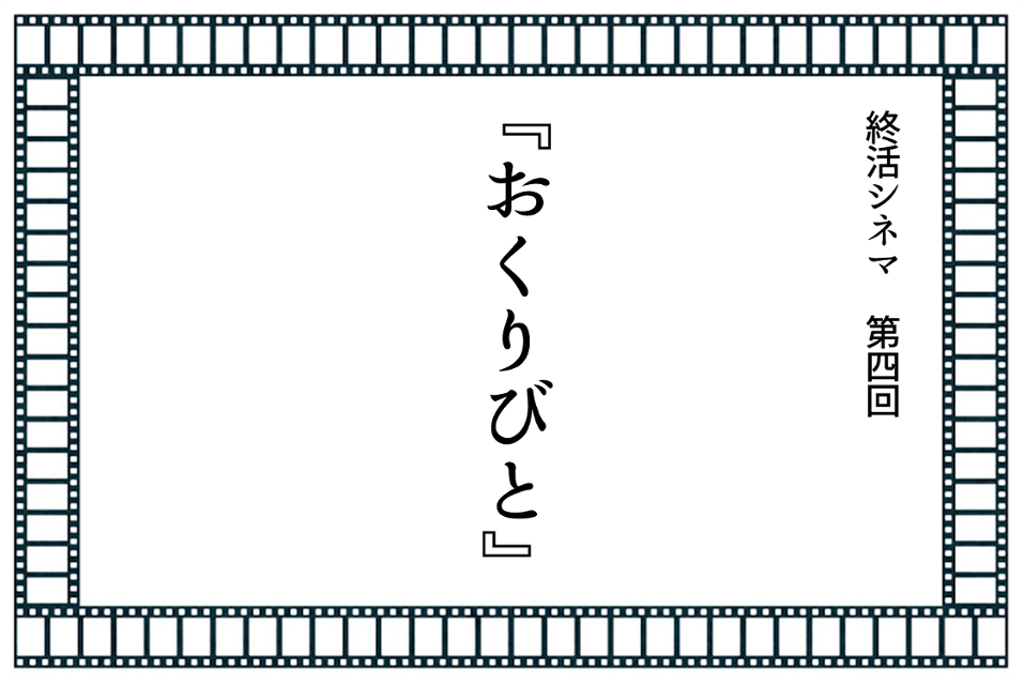数ある終活映画の中でも、まずご案内したい映画のひとつに『おくりびと』があります。
第81回アカデミー賞外国語映画賞を獲得したことでも、世界的に有名な映画です。
滝田洋二監督により2008年に劇場公開になった映画ですが、東京の下町の劇場に出かけた私は、当時の映画館では珍しいほどに公開初日に立ち見に並ぶ諸先輩方を目にしました。
当時はまだ、超高齢化社会が言われ始めたころ。「終活」という言葉が一般に知られるどころか、まだ話題に取り上げられることもない、そんな時代(?)でした。
「死は穢れ」と教わってきた私たちに映画が教えてくれること
ゆっくりと流れる大自然の時間の中で、人はいろいろと悩み苦しみます。
生老病死もその一つとして、死別による悲嘆とそこにある癒しを感じさせる文化や人の繋がりを感じることができる映画です。
映画の中では、死者に触れる納棺師の夫に「汚らしい」という言葉でその手を拒絶する妻がいます。死を穢れとして習ってきた私たちの畏敬の念。
それを解くように施される納棺師の所作や、人とのかかわりはまさに、次の成長の切っ掛けなんだと、教えてくれる映画です。
はじめての納棺の場面
私がぜひ見ていただきたいシーンは、実は主人公が初めて納棺夫に付き添って出かけた家での出来事です。
5分遅刻した納棺夫に、やり場のない思いをぶつける妻を亡くしたご主人。
着せ替え化粧が施されている間、彼はじっと妻を見つめるだけでした。
「お使いになっていた口紅はありますか?」
納棺師のこの問いにも、「無え」と一言だけ。
でも、その時、傍らにいた娘が母の口紅をもってくるのです。
やがて納棺の儀式が終わり、妻の眠る棺のふたがまさに閉じられようとしたとき、彼は声を出して泣き出すのでした。
一人ひとりがそれぞれに違う人生でありドラマをもって生きているということ。
当たり前のことなのについつい忘れそうなことを、納棺夫の仕事を通じて思い出した主人公でした。
そしてその先に遭遇した父の死で彼はどんなことを考えたのでしょう?そんな葛藤や悩みも関係なく山形の大自然は流れてゆくのです。
一つひとつのシーンに自分を置いてみることができる映画です。
超高齢化社会に向かって行くときの畏敬の念を持った日本人の死生観がほんの少し変化して、超高齢化社会により終活が大きく話題になったと同時に、そんな風に映像に身を置いて楽しんでみてはいかがでしょう。大きな社会変化をもたらした、まさに「終活映画」だと思います。
いつもそこにいるのが当たり前の妻のことでも、果たして自分はどこまで知っていたのだろうか?
ある日突然に失った人のその存在の大きさ程のこころの穴を、人はどのように整理をするのでだろうか?
そんなことを自分と家族に置き換えて考えてみると、また少し意味のある終活に取り組むことができそうだと思いませんか?
今回ご紹介した映画『おくりびと』
公開:2008年
監督:滝田洋二郎
脚本:小山薫堂
出演: 本木雅弘、広末涼子、余 貴美子、吉行和子、笹野高史、山崎努、山田辰夫 ほか
この記事を書いた人
尾上正幸
(終活映画・ナビゲーター / 自分史活用推進協議会認定自分史アドバイザー / 株式会社東京葬祭取締役部長)
葬儀社に勤務する傍ら、終活ブーム以前よりエンディングノート活用や、後悔をしないための葬儀の知識などの講演を行う。終活の意義を、「自分自身の力になるためのライフデザイン」と再定義し、そのヒントは自分史にありと、終活関連、自分史関連の講演活動を積極的に展開。講演では終活映画・ナビゲーターとして、終活に関連する映画の紹介も必ず行っている。
著書:『実践エンディングノート』(共同通信社 2010年)、『本当に役立つ終活50問50答』(翔泳社 2015)