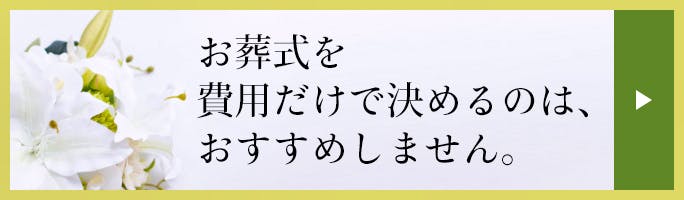互助会とは、冠婚葬祭にかかる費用の一部を毎月前払いで積み立てておくことで、利用時に会員価格で質の高いサービスを受けられるシステムです。
リーズナブルに葬儀を執り行えることや、互助会によっては提携施設の割引を受けられるなど、互助会制度には多くのメリットがあります。
しかし最近では、冠婚葬祭の傾向が変わってきたことで解約の依頼も増加傾向。解約手数料の高さや手続きのわずらわしさなどの問題で、トラブルとなるケースもあるようです。
今回は、互助会についてのメリットやデメリット、また解約する場合の手順や解約手数料について解説していきます。
互助会とは

将来の冠婚葬祭にかかる費用の一部を毎月、事前に積み立て。冠婚葬祭で利用する際には会員価格で安価に高品質なサービスが受けられるのが、互助会のシステムです。
葬儀が必要になった際には、積み立てた金額に応じて冠婚葬祭のサービスを受け取ることができます。※サービスの内容は互助会によって異なります。
互助会制度は経済産業省に許可された事業であり、契約内容は一生補償されます。
互助会のメリット
急な出費のために、毎月安価で備えられる

葬儀は突然起こり得るものです。そんなとき、あらかじめ積み立てていた互助会を利用すれば、急な出費をおさえることができます。
冠婚葬祭に関するさまざまなサービスを受けることができる
冠婚葬祭に関するさまざまなサービスを、会員ならではの割引価格で利用できます。葬儀や結婚式だけでなく、七五三や成人式などでもサービスを受けられる互助会もあります。
あわせて読みたい
加入者だけでなく家族もサービスを受けられる
互助会では、契約プランによるものの、互助会加入者だけでなくその家族もサービスを受けられるのが一般的です。
設備が充実した施設を利用できる
互助会で利用できる施設は、豪華絢爛な設備や調度品も整っていることが多く、質の高い葬儀を執り行うことができるのが特徴です。参列者への会食料理や返礼品なども、豪華なものを提供するところが多く見られます。
互助会のデメリット
選べる葬儀社やプランが限定される
互助会に加入する際は、ある程度定められたプランから選ぶことになります。また、加入後に葬儀を執り行う際には、互助会の葬儀社しか選ぶことができず、「自宅の近くの葬儀場を利用したい」「故人を満足に見送れる葬儀社を選びたい」といった希望が叶えられない場合があります。
積み立てても全ての費用をまかなえない場合が多い
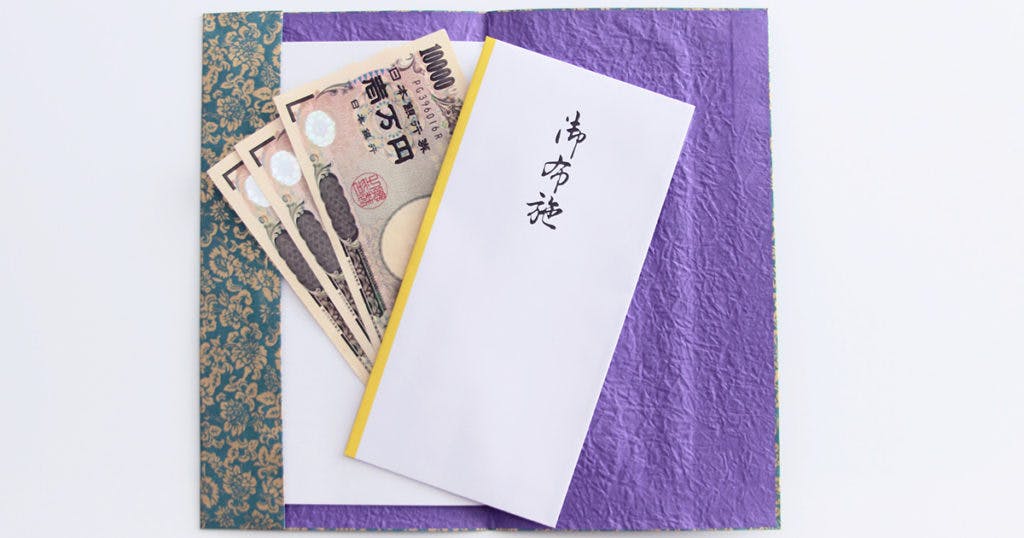
互助会の契約プランの満期を迎えていても葬儀や結婚式の費用全額を積立金でまかなうのは難しく、追加費用を支払わなければならないケースが多くあります。「互助会に入れば安心」と思う方も多いかもしれませんが、金銭のトラブルになることも。
また、葬儀での豪華な提灯など不要と思われるようなサービスが含まれていても、差額を返してもらうことはできません。
加入している互助会が倒産する可能性もある
互助会は民間企業が運営しているため、例えば会員数が減少して経営が悪化したりすれば、倒産することもあり得ます。もし加入している互助会が倒産した場合、積立金は支払った金額の半分しか返ってきません。最終的に大きい金額を積み立てるわけですから、互助会への加入はある程度のリスクを考える必要があります。
積立金はサービスでしか還元されない
互助会の積立金は、葬儀や結婚式などのサービスへの利用に限られます。銀行預金などのように現金として引き出すことはできません。
解約手数料がかかる
互助会の解約には解約手数料が発生します。解約手数料は契約内容や支払回数などに基づいて計算されます。
互助会の解約方法と手順

「互助会の解約はできない」「難しそう」と思う人もいるかもしれませんが、解約することは可能で、契約に基づいて積立金が返金されます。ここでは、解約の理由や必要なもの、手順などを確認しましょう。
互助会を解約する理由
上記のように、互助会には大きなメリットがある一方、デメリットもあります。また、加入後に心境や状況が変化したことで「別の葬儀場を利用したい」「経済状況が変わって掛け金を払うのが難しい」と思うようになるなど、互助会の解約にはさまざまな理由があるようです。
また、最近では葬儀、結婚式ともに費用をおさえたプランに人気が出てきています。「身内だけでの葬儀、結婚式で十分」という方も。そのような理由で、互助会の解約を検討する人もいます。
解約に必要なもの

解約の手順
解約手続の方法も各互助会により若干異なります。予め事前に電話などで確認し、手続に必要なものを準備のうえで行くのが良いでしょう。加入者本人以外が解約手続きを行う場合
互助会の解約手続きは加入者本人でなくても行うことが可能。解約の手順は本人が行う場合と同じですが、加入者本人の委任状が必要です。
また、加入者が亡くなった後に家族が互助会の存在に気づく場合や、加入者が自分で手続きできない場合もあります。そのような場合は、加入者の除籍謄本や、代理人の戸籍謄本などを必要とする場合があります。
互助会の解約に伴う返金額と期間

では、実際に互助会を解約した時の返金額はどれくらいなのでしょうか。最近では互助会を利用しなくても、安価で充実したサービスを受けられる葬儀場も増えています。解約手数料を払ってでも希望の冠婚葬祭会社を利用した方が安くなる場合もあるので、よく検討するのが良いでしょう。
解約手数料の目安
互助会の解約手数料の目安は、最大で完納金額の2割程度と言われています。この金額は加入時の契約に基づいて計算されますが、互助会への加入の時期や解約の時期(支払回数)などによっても異なります。
返金額の計算方法や解約手数料に疑問がある場合は、互助会に問い合わせて確認すると良いでしょう。
返金までの期間
実際に返金されるまでの期間は、一般的には解約が受理された日から45日以内とされています。ただし、互助会によって前後します。
互助会の解約に関するトラブル
互助会の解約について難しい手続きはありません。しかし互助会に「解約をしたい」と伝えても、スムーズに受け付けてもらえない場合があります。
なかなか解約できず対応が難しい場合は、国民生活センターや経済産業省の窓口などに相談しましょう。また、互助会解約の代行サービスを利用するという手もあります。こちらを利用する場合代行手数料がかかってしまいますが、精神的な負担少なく解約してもらえます。