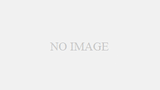社葬とは、会社が運営主体となって執り行われる葬儀のことです。社葬と聞くと大きな会社が執り行うイメージがありますが、社葬には税制上のメリットなどもあり、中小企業や自営業の方にもおすすめの形式です。
社葬と他の葬儀との違いは何か、社葬の目的、社葬の形式にはどのようなものがあるか、社葬を運営する際のポイント、社葬に参列する時のマナーなどについて詳しく紹介しています。
目次
社葬と一般葬の違い
会社が施主となって執り行う葬儀を社葬といいます。社葬の対象となるのはそれぞれの企業によっても異なりますが、一般的には会社の創業者や、会長、社長、役員などの経営陣、また会社に大きく貢献した方や、業務中の事故で亡くなった方となります。会社が主体となって執り行うため、個人が執り行う一般葬とは、下記のような違いがあります。
社葬の施主と喪主、葬儀委員長の違い
喪主は葬儀の打ち合わせをしたり、葬儀で挨拶をしたり、弔問を受けたりなど、葬儀を取り仕切る人です。
一方、施主は主に葬儀の費用を負担し、葬儀を運営・サポートする責任者のことです。通常、一般葬では遺族が喪主を務め、施主も兼任しますが、社葬では喪主は遺族、施主は会社が担い、葬儀委員長を会社の社長や重役が務めます。葬儀委員長は、会社を代表する社葬の最高責任者であり、実質式の中心的な存在となっています。
社葬の費用負担
一般葬では葬儀に関わる費用を喪主や親族が負担しますが、社葬では葬儀に関わる費用の全額または一部を会社が負担します。大企業などでは、役職や後席によって負担する費用や範囲を社内規程で定めている場合もあります。
社葬で費用として認められる項目
- 訃報通知の新聞広告料
- 案内状の作成・発送費用
- 祭壇料
- 葬儀場の使用料
- 宗教者へのお礼(お布施など)
- 参列者へのハイヤー代および送迎バス代
- 参列者への御礼(礼状および粗品)
- 社葬・合同葬を手伝った社員に対する簡単な慰労会費用・食事代
- 葬儀社警備などの人件費
- 写真・ビデオ撮影料など
社葬に関わる費用は、福利厚生費として損金算入することができます。税法上認められるのは、故人の会社に対する貢献度や亡くなった事由が、社会通念上相当と認められる場合です。社葬に関わるすべての費用が損金算入されるわけではなく、戒名料や墓石の購入費用など、認められない費用もあります。
また、損金算入するためには、社葬で執り行うことを取締役会で決定し、取締役会議事録に残す必要があります。
社葬を行う意味と目的
一般葬も社葬も、故人の死を悼み、遺族の悲しみを慰めるという目的は同じですが、社葬を執り行うことにはそのほかにも大切な目的があります。
社葬は、社内外に故人の功績を称え、故人の会社に対する想いを引き継いでいく意思をアピールする場でもあります。また、代表者が亡くなった場合は、後継者が取引先や社員など、関係者に対して事業の承継を宣言する場でもあります。
今後の体制が盤石であるということを示すためにも、社葬を滞りなく運営することが重要です。社葬が、今後の会社のイメージを左右することもあります。
社葬の種類

社葬には、遺族による密葬が終わった後に日を置いて行われる一般的な意味合いでの「社葬」と、遺族と会社が合同で行う「合同葬」、宗教色や儀式性をおさえた「お別れの会」があります。
合同葬とは
合同葬は遺族と企業が合同で執り行う葬儀です。
おおよその流れは一般葬と同様、それぞれの地域の慣習にそって、火葬前の遺体を前に通夜や葬儀・告別式を行うのが一般的です。
中小企業などの同族会社で多く見られます。葬儀費用の負担や葬儀の運営の仕方については、会社と遺族が話し合って決めます。スケジュールが厳しい場合もありますが、葬儀が一回で済むため遺族や参列者の負担がおさえられるというメリットがあります。
社葬とは
一方、社葬は企業が施主となります。喪主や遺族は社葬に出席することはありますが、運営にはかかわらないのが一般的です。遺族や親せき、親しい方々とのお別れはすでに行っているため、より企業色の強い葬儀となります。
お別れ会とは

お別れ会は、社葬の名称が変わったものです。特に定義があるわけではなく、内容も社葬と大きく変わることはありませんが、社葬と比べ、宗教儀式を廃して、故人の業績を称え告別することを主な目的とすることが多いようです。
また、ホテルの宴会場などを会場に参列者を会食でもてなし、故人の業績を展示するブースを設けたり、映像を流したりするなど、演出等の自由度がより高くなる傾向もあるようです。お別れの会、偲ぶ会と呼ばれることもあります。
最近では、家族葬や密葬、直葬(火葬式)といった、近親者など身内のみで行う葬儀が増えてきています。 遺族は弔問客の相手で身体的にも精神的にも疲れてしまって、故人とゆっくりお別れできないことがあるからです。
「家族葬(あるいは直葬)」と「お別れの会」の2段階で執り行うことで、故人に関わる多くの人が納得できる葬送の形ができあがるという考え方もあります。
社葬を運営する上での注意点
一般的には社葬とお別れ会は、葬儀とは別に四十九日法要の前に執り行われます。日程に余裕があるため、葬儀委員会の設置や関係者への案内、当日の進行の打ち合わせなど、体制を整えた状態で執り行うことができます。
どんな形式で社葬を執り行うとしても、大切にしなければならないのは遺族の想いです。社葬を執り行いたい場合は、故人が会社に貢献していたこと、仕事の関係者も多く参列できること、費用を会社が負担することなどを遺族に説明しましょう。
それでも遺族が社葬を辞退された場合は、遺族の想いを尊重し、最善の対応を考える必要があります。
社葬の流れ①事前準備と遺族の打ち合わせ
社葬は会社の行事ですが、もちろん家族の意志を尊重して進めることも大切です。
社葬が決まったら、葬儀委員長はみずから喪家に出向き、遺族の意向を確かめたうえで、綿密に打ち合わせを行いましょう。日程、葬儀の形式のほか、葬儀費用の負担の仕方についてもよく相談しあうことが重要です。遺族との連絡をより円滑にするためにも、葬儀委員会は専任で連絡係を選出しておくと良いでしょう。
社葬の準備
式場は社葬の規模、交通、宗教の形式などを考慮して決めます。式場が決まっていないと、はっきりとした日程や段取りを決めることができないため、式場の手配を最優先にしましょう。
葬儀の日取りと式場が決まったら、葬儀業者と連絡を取り参列者の予定数、予算、日程などを示して打ち合わせする必要があります。
社内で掲示するだけでなく、遺族と相談し故人の友人、知人関係についても漏れのないように連絡先名簿を作るのが良いでしょう。その際、見積書の提出をお願いし、葬儀費用を概算しておくことが重要です。
喪主は通夜の前に決める
喪主とは、遺族を代表して葬儀を執り行い、故人に代わって弔問を受ける人のことを指します。葬儀の通知を喪主の名前で出すことになるため、通夜の前に喪主を決める必要があります。
以前は、法律上での相続人が喪主になるものとされていましたが、今日では故人ともっとも血縁の濃い人が務めることが一般的とされており、また、タブーとされてきた年上の方が喪主になる「逆縁」は今では不問です。
社葬の流れ②当日までに行うこと
ご逝去直後に最も注意したいのは、ご家族への対応です。
会社としては社葬執行に向けてスピードを求めがちですが、悲しみの只中にいるご家族への配慮を忘れてはいけません。担当者は社葬取扱規程に沿って速やかに行動しつつも、丁寧にご家族に寄り添い、できる限りサポートを行うことが大切です。
ご逝去直後の社内対応
訃報を受けたら、緊急連絡体制、緊急連絡網に基づき、各関係者へ連絡していきます。深夜に訃報が入った場合など、連絡すべきタイミングかどうか迷うことがあるため、あらかじめ急いで知らせるべき担当者や部署を決めておくと良いでしょう。
社外に情報が漏れると、葬儀に関する問い合わせが殺到したり、ご家族に迷惑がかかるケースもあります。ご逝去直後の連絡範囲や伝達内容を、社葬対応マニュアルにまとめて社内で共有しておきましょう。主な伝達内容は、亡くなった人の名前、年齢(享年)、逝去日などです。
緊急役員会の開催
ご家族の同意が得られ、正式に社葬の執行が決まったら、社葬取扱規程に沿って、速やかに準備を進めていきます。
まずは社葬における基本方針を決めるため、緊急役員会を開きます。緊急役員会では、社葬の執行から規模や形式、葬儀社の決定などを行います。社葬取扱規程で定めておいたものは、あくまでも概算や想定になるため、実際の社葬にかかる費用や人員などは、その都度承認のための決議が必要になります。
社葬までの限られた時間の中で、緊急役員会を迅速に遂行するために社葬取扱規程が役立ちます。また、緊急役員会の議事録は社葬費用を経費として計上するために必要です。忘れずに作成しておきましょう。
- 社葬執行の決定
- 社葬の規模と形式の決定
- 社葬の日時と場所の決定
- 葬儀実行委員長の決定
- 概算予算の決定
- 香典や供花、供物の決定
- 葬儀社の決定
社内通達・社外通知
新聞などに訃報記事が出たり、どこかから訃報が漏れると、外部関係者から問い合わせが殺到することがあります。問い合わせの対応に追われる事態を最小限におさえるために、社内の情報伝達や共有は迅速に行う必要があります。
まずは、緊急役員会で決定した基本方針を社内に通達するため、担当部署から社葬に関する社内伝達文を全社員に提示します。社内伝達分を提示することで、社外からの問い合わせに対して統一した回答が可能になります。万が一、対応の仕方が分からないことがあった場合のために、各担当者の連絡先を共有しておくと安心です。
また、社葬に参列する社員の範囲を決定し、通達することも必要です。社葬に参列しない社員には、黙祷の時間を作ったり、支社や工場などの遠隔地の社員のために、別に拝礼の場を設けることもあります。その範囲に入らない一般の社員の中にも、最後のお別れをしたいということで参列を希望する人もいます。そのため、例えば総務部あてに申請することで、参列できることなども通達します。もちろん、社員の全員参加という企業もあります。また服装や参列の注意事項なども含まれるので、通達は複数回に分けて伝えるのがよいようです。
社葬に参列しない社員は、当日の朝礼の時に弔意を表す黙祷をする企業がほとんどです。またお客さまに対応する社内の社員だけ喪章を付け、喪に服す姿勢を社外に示すところもあります。供養の場として社内のロビーなどに故人の写真や花などを飾った仮祭壇を用意するところもあります。
社外通知に関しては、社葬連絡簿に基づいて案内状を送ります。新聞に訃報記事を載せる場合は、葬儀社か新聞社に直接連絡を入れましょう。
重要な取引先への通知
一般的には重要な取引先などの来賓や関係団体のトップ、故人と親しくしていた政治家などVIPには、社葬の案内状を発送します。届いたのを見計らって確認の連絡を入れます。基本的には出席できない場合は代理人が出るような形を取ることになっています。また葬儀式と告別式を分けて行うときには、告別式の案内状を出すことが多いようです。
原則として挨拶文は書かずに、葬儀または告別式の日時、場所、葬儀委員長、喪主、問い合わせ担当部署などを記入するだけにします。
社葬の周知ということでは、新聞に広告を掲載する企業も多いようです。葬儀の日時・場所などが決定したら、広告とは別にパブリシティという形で各新聞社などに社葬の情報をプレスリリースすることで記事として取り上げることもあります。なお社葬の広告は、式当日の2週間前ぐらいに掲載するのがタイミングとしては良いようです。案内状は社葬の広告掲載の日よりも遅れないように調整します。
社葬進行要領を決定する
社内通達・社外通知が終わった後、最も重要なのは、社葬進行要領を決定することです。社葬進行要領とは、葬儀実行委員長の指揮のもと、葬儀実行委員が中心となり、社葬当日の流れをイメージしながら、必要事項を具体的に決めていくことです。社葬の形式に応じた式次第やタイムスケジュールの作成、葬儀実行委員会の編成や役割分担、席次や拝礼順などを詰めていきます。
葬儀実行委員は、来訪対応係や遺族対応係、返礼品対応係や駐車場係などの係に分かれて動きます。総務や人事、秘書などの担当者は、葬儀実行委員の各係と連携を取りながら、弔辞の奉読依頼や案内状の送付などを進めます。名簿を作成し席順を決め、一般会葬者数を予測して、座席の数や駐車スペースを確保します。
社葬前日にはリハーサルを行い、社葬進行要領に従って、動線や時間配分を確認します。葬儀実行委員長が受付やクローク、席順や席数、供花や供物など、全体をチェックし、葬儀実行委員会のメンバー全員で最終打ち合わせを行います。
社葬の流れ③社葬当日に行うこと
社葬当日は、式の2~3時間前に集合し、それぞれの係の役割を再点検します。
葬儀委員長をトップに、実行委員長を中心に当日は進めていきます。葬儀実行委員は、担当別に最終打ち合わせを行い、各自の持ち場や動線をチェックし、配置につきます。遺族が到着したら、葬儀委員長、喪主、遺族で式の進行について確認。葬儀実行委員長は供花や供物などに不備がないかを調べ、奉読する弔電を選んで順番を決めておきます。
開式15分前には、葬儀実行委員長、喪主、遺族、来賓は席順に従って着席します。
一般的な社葬の流れ
- 開式の辞
開式を宣言するためのものです。司会者もしくは葬儀副委員長などが行う場合が多いようですが、省略されるケースもあります。短く簡潔にまとめ、必要に応じて「誰の葬儀であるか」「どのような形式で行うか」を明確にします。 - 黙祷
黙祷とは、声を出さずに心の中で、対象に祈ることです。社葬は、一般的には業務時間内での施行のため、役員と係員のみの参列が多いですが、参列できない社員のために、社葬開始時間に合わせて黙祷を行うケースもあります。 - 故人の経歴紹介
故人の生年月日や学歴、入社年月日、その後の職務経歴、会社で果たしてきた役割や上げてきた成果、業績などと絡め、周囲からの見た印象や人柄、性格などを紹介します。 - 弔辞
弔辞とは、故人へかける最後のお別れの言葉です。弔辞奉読者は、葬儀委員長、取引先、友人代表、社員代表など3~4人。時間は4~5分くらいにまとめるのが一般的です。 - 弔電奉読
弔電は、社葬に参列できない場合に打つお悔やみの電報です。弔電が多いときは2~3通に絞ります。事前に読み上げる順番や会社名・お名前などの読みを確認しておきましょう。 - 葬儀委員長謝辞
社葬の主催者である葬儀委員長の挨拶です。故人との関係を簡潔に述べ、故人の生涯や人柄、業績を伝え、最後に参列してくれた人への感謝の言葉で結ぶのが一般的です。 - 喪主挨拶
故人の家族を代表する形で、喪主が故人の代わりに、会葬者に向けて参列に対するお礼の言葉を述べます。重ね言葉や禁句などはありますが、感謝の気持ちを伝えることが重要です。 - 葬儀委員長献花
献花・焼香いずれの場合も、葬儀委員長から始めるのが一般的です。花側を右手に受け取り、茎側が献花台へ向くように持ち替え、そのまま献花台へ供えます。遺影を仰いで黙祷を捧げ、遺族に一礼し、自席に戻ります。 - 喪主献花
葬儀委員長に続き、喪主が献花を行います。葬儀委員長や喪主は、社葬の重要な役割を担う人です。謝辞や挨拶だけでなく、献花・焼香も事前に手順を確認しておくと良いでしょう。 - 遺族・親族献花、来賓・会葬者献花
会葬者の多い社葬の場合は、遺族・親族、来賓の献花は代表者までとし、それ以外の方や会葬者は、複数人まとめて献花・焼香を行うケースもあります。 - 閉式の辞
閉式を宣言するためのものです。開式の辞同様、司会者もしくは葬儀副委員長などが行う場合が多いようですが、省略されるケースもあります。短く簡潔にまとめましょう。
葬儀実行委員の当日の役割
葬儀委員長
社葬の統括最高責任者です。会長が亡くなった場合には社長が、社長が亡くなった場合には副社長が務めるなど、会社の序列によって選出されます。所属組合の理事長や親会社の社長など、社外から選ばれる場合もあります。
社葬当日は、遺族到着時と出棺時の葬列の先導を担当します。喪主に先立って焼香を行うほか、参列者に謝辞を述べたり、故人の経歴を紹介し、功績を称えるなど、社葬の表舞台での中心的役割を担います。
葬儀実行委員長
社葬を実行するために設けられた、葬儀実行委員会のトップを務めるのが葬儀実行委員長です。社葬全般を取り仕切り、葬儀実行委員を選出し、各係の統制を行い、社葬後の実務処理までの責任を持ちます。普段から経営層のサポートを行うだけでなく、各部署とのコミュニケーションが欠かせない立場上、総務部長が向いているとされています。
社葬当日は、運営本部係の責任者として、社葬全体を見守り、不測の事態に備えます。
葬儀実行委員
葬儀実行委員長によって選出され、受付係や式場案内係、接待係など、社葬業務に関わる各セクションの責任者を務め、それぞれのセクションで社葬業務に携わるメンバーを選任し、まとめます。葬儀委員は企業側の代表ともいえます。
社葬の実施日程や場所、遺族や参列者の人数、供花・供物、香典受諾の有無など、それぞれのセクションで、社葬の実施に関わる具体的な内容を決定し、準備から実行までを行います。
出棺時は式場入り口で整列して棺を見送ります。 喪主(遺族)は、葬儀委員長を先導に位牌、遺影、棺、親族の順に入場します。出棺時も同様に、葬儀委員長を先導に、位牌、遺影、棺、親族、そして葬儀委員の順に葬列を組みます。
葬儀実行委員長を責任者とし、社葬業務の統括や実務管理を行い、葬儀社や遺族、経営層との打ち合わせなどを担当します。
社葬当日は、実行本部に詰め、各係への指示伝達や、各係から入る連絡の中枢を担います。不測の事態が発生した場合には、各係員に適切な指示を与えます。司会者とは密に連絡を取ることのできる連絡係などを決めておきます。連絡係はメモ用紙を常に携帯し、連絡事項を口頭で伝えとともにメモを手渡すことでより確実性が増します。
受付係は、参列者名簿に従い、遺族や来賓、葬儀参列者や一般会葬者などの受付や、当日式場に届いた供花や供物、弔電などの受付と併せて、会葬者芳名帳や名刺の整理を行います。また、社葬終了時には、会葬礼状と粗供養品を渡します。取引先関係、業界関係、親戚・友人関係などに分けて設置することで、よりスムーズな対応が可能になります。
クローク係は、来賓や葬儀参列者、一般会葬者の荷物を預かり、終了後には返却する役割を担います。丁寧で確実な対応が求められます。
葬儀委員長や喪主、遺族や弔辞者などの席次や、席札の名前の確認を行います。
遺族や来賓、葬儀参列者や一般会葬者を、各控室や待合所などへ案内するだけでなく、開式時間が迫ってきたら、式場の正しい座席に誘導します。また、僧侶などの宗教者を控室に先導し、葬儀開始の際には式場へ案内する役割も担います。
焼香時には、葬儀参列者や一般会葬者を順番に誘導し、焼香を終えて帰られる方には、会葬礼状と粗供養品をお渡しするため、受付に案内します。
遺族や来賓、僧侶や参列者、一般会葬者などに対し、各控室や待合室で接待を担当します。軽食や弁当がある場合は配布と回収、葬儀終了時には、おしぼりの配布と回収などを行います。遺族係や僧侶係などと決めておくとスムーズに対応できます。 式場では式場内係、会葬者誘導係、救護係などの各セクションを設置します。
供花や供物を名札に従い、配列順に沿って並べます。
式場レイアウトをもとに、式場内の祭壇や座席、メモリアルコーナーや飾り付けなど、式場内の設営に不足しているものはないか、レイアウト通りに配置されているかなどの確認や点検を行います。
写真やビデオなど、社葬全般の撮影を担当します。カメラなどの撮影機器の準備や点検は入念に行います。事前に式次第を確認しながら、あらかじめ撮影のポイントを決めておくとよいでしょう。
遺族や来賓、参列者や一般会葬者だけでなく、供花や供物は名札が判るように撮影し、祭壇やメモリアルコーナー、受付なども撮影し、記録として残します。
写真やビデオによる記録のほか、文書による記録もしておきましょう。あとになって企画されることもある追悼録の製作や、慰霊碑建設などにも役立ちます。次の世代に引き継ぐ大事な記録にもなり、将来的に発生する社葬のお手本にもなります。なお、式典中の撮影ではなるべく参列者の迷惑にならないようにしましょう。
駐車場係は、会葬者数を想定して適切な駐車スペースを確保し、駐車場での車の誘導や整理を行います。また、マイクロバスやハイヤーの誘導や、乗車・下車位置でのドアの開閉、乗車者・下車者の案内などを担当します。
場外案内係は、最寄り駅や式場までの道路に立ち、地域の住民や事故防止に配慮しながら、参列者や一般会葬者の案内を行います。
社葬の流れ④社葬終了後に行うこと
社葬終了後は、社葬でお世話になった方への御礼の挨拶と、名簿や報告書などの記録や整理という重要な仕事が残っています。社葬後の事務処理は、葬儀実行委員で役割分担して行います。会葬者名簿や社葬報告書、会計報告書を作成し、社葬に関する記録として、大切に保管・管理します。
弔辞奉読をお願いした方への御礼の挨拶は、よほど遠方でない限り、会社の代表者が直接出向きます。供花や弔電をいただいた方には、御礼状を送りましょう。
御礼の挨拶回り
社葬でお世話になった方への御礼の挨拶は、社葬における最も重要な仕事のひとつです。社葬終了後、3日以内を目処に、なるべく早く御礼を伝えましょう。
弔辞奉読をお願いした方や来賓への御礼の挨拶は、よほど遠方でない限り、会社の代表者が直接出向きます。供花や弔電をいただいた方には、御礼状を送りましょう。新聞に会葬御礼広告を掲載することで、会葬に対する御礼を表明する場合もあります。
社葬は、顧客や株主、取引先など、会社に深く関わる方たちに、会社の新体制や今後の方針など「これからの姿」を印象づけ、信頼関係を継続させるための広報的な役割を担っています。会葬の御礼の挨拶までしっかりと行い、最後まで礼を尽くすことで、社葬の成功を強く印象づけられるでしょう。
社葬後の事務処理
弔辞・弔電の整理
弔辞・弔電はコピーを取るか、会社名、役職名などを整理し、リスト化した後、保管・管理します。現物とリストは遺族に渡します。
会葬者名簿の整理
会葬者の名刺や記録(芳名)カードなどはコピーを取るか、リスト化した後、保管・管理します。現物とリストは遺族に渡します。
香典・供花・供物などの整理
香典や供花・供物などをいただいた場合は、金額といただいた先の名称などを記録し、会社別に整理し、リスト化した後、保管・管理します。現物とリストは遺族に渡します。金額別に、住所・氏名・電話番号・郵便番号などをリスト化したものは、返礼品を送る際に、遺族の大きな助けになります。
会計報告書の作成
必要経費の内容を確認し、葬儀社、式場、関連業者などへ支払いを行います。その後、全体の費用を総括し、会計報告書を作成し、保管・管理します。
社葬報告書の作成
社葬全体の報告書を作成し、葬儀実行委員長に提出します。また、必要に応じて関係者に配布します。その後、写真や映像などの記録、各リストなどと併せて、会社で保管・管理します。
退職金や給与の精算など
退職金の支払い
在職中に死亡した場合は、会社の就業規則や退職金規定、中小企業退職金共済法などにおける算定方法により、退職金が支払われます。死亡退職金は所得税、住民税が非課税ですが、相続税の対象になります。
故人が役員だった場合に支払われる慰労金は、会社として遺族に弔慰を示すものなので、香典相当額内であれば株主総会の決議は必要ありませんが、香典相当額を超える場合や退職金に関しては、株主総会の決議が必要になります。
給与の精算
在職中の死亡の場合は就業規則に基づいて給与を精算し、総務は、その年の1月1日から死亡日時までの給与の額等を記載した源泉徴収票を発行します。また、未払いの給与や交通費など、生前に使用し、支払われていない経費があれば精算します。
源泉徴収票の発行
相続人、もしくは故人から包括遺贈を受ける人が、所轄の税務署にて所得税の準確定申告を行うために、源泉徴収票が必要になります。総務は速やかに発行しましょう。所得税の準確定申告は、4ヵ月が期限となります。
保険関係の手続き
遺族への埋葬料や、遺族年金の手配を行います。健康保険や厚生年金保険の被保険者資格喪失手続き、埋葬料の請求は、社会保険事務所か健康保険組合で行います。
また、業務上の死亡の場合は、労災保険より遺族給付や葬祭料などが支給されますので、申請手続きをします。故人が団体生命保険に加入している場合は、保険会社に生命保険の受給請求を行います。
社内預金や財形貯蓄の精算
故人が生前、社内預金などを行っていた場合は精算します。財形貯蓄を行っていた場合は、取り扱い金融機関に連絡します。
慶弔金規定がある会社の場合は、弔慰金の支払いについて確認し、その手配を行います。
叙勲の申請
故人が社内や業界で大きな功績を上げている場合、その栄誉を称える叙勲を申請できます。
通常は逝去後速やかに手配し、社葬で祭壇に勲記・勲章を飾りますが、社葬後に申請することも可能です。手続きは、死亡日から30日以内に閣議決定・裁可が完了するように制限が課せられていますが、避けられない事情により手続きが30日を越える場合は、遅延理由書を提出する必要があります。
社葬に参列する際のマナー

社葬は会社だけでなく、故人や遺族にとっても大切なイベントです。会葬者として社葬に参加する場合は、失礼のないようにしましょう。
服装は、男女とも略礼服と呼ばれる喪服で参列します。「お別れ会」などの場合、案内状に「平服でお越しください」と書かれていることがあります。
その場合は、男性はダークスーツ、女性は黒や紺など、地味な色のスーツやワンピースがおすすめです。アクセサリーをつける場合は、パールを選ぶようにしましょう。それぞれの企業の特色や、その企業の属する業界の風潮などもあります。そうした企業文化なども考慮しながら、ふさわしい服装を心掛けましょう。
社葬の弔電とお香典
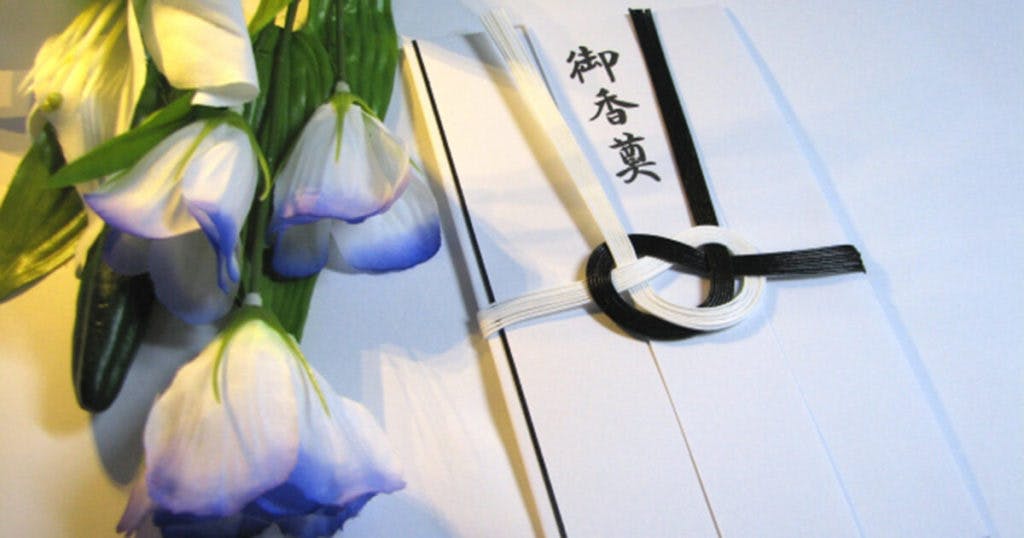
個人葬の場合、弔電の宛先は喪主とされるのが普通ですが、社葬の場合は弔電の宛先は葬儀委員長となっています。合同葬の場合は喪主や遺族でも相違ありません。
また、お香典に関しては喪主宛てとなります。これは社葬の場合お香典が税金対象となることから、辞退するのが一般的とされているためです。